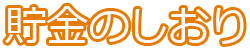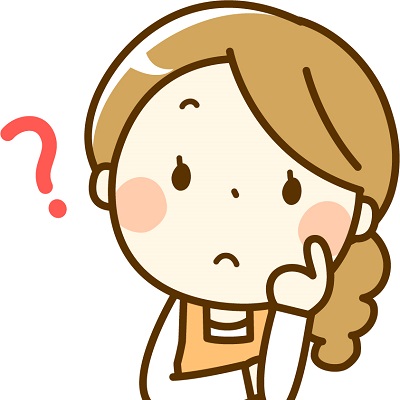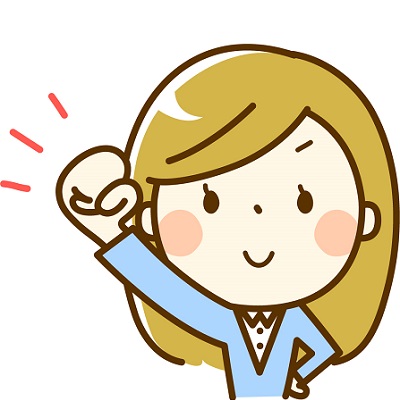貯金ができない原因を『収入が少ないから』と考えている人もいるでしょう。確かに収入が少ないと貯金に回すお金が少なくなかなかまとまったお金が貯まりませんよね?
しかし貯金のコツをしっかり押さえて取り組めばたとえ低収入であっても貯金はできます。
当ページでは低収入の人でも貯金を成功させるコツを7つ紹介します。もし“収入が少ない”を理由に貯金を始められないのであれば、まずは7つのコツを習慣づけるところから始めてみてはいかがでしょう。
目次
貯金の目標金額を決める

貯金を始めるのであればまず
という目標を決めましょう。貯金の目標金額が明確になっていると“ゴール”がはっきりするため貯金に対するモチベーションが落ちにくく継続して取り組めるようになります。
とはいってもいきなり数千万単位の金額を目標にする必要はありません。
特にこれまで何度も貯金を始めては挫折した人は“頑張ればできそうな金額”を目標にすると達成しやすくなります。また低収入の場合、そもそも貯金に回せる金額自体が決して多くありませんから貯金を始めてから1~2年くらいで達成できる金額をゴールに据えるといいでしょう。
具体的に貯金の目標金額を決める基準としては次の4つのいずれかがおすすめです。
“とりあえず”100万円
・・・という人の多くが100万円を目標金額として設定すると思います。ある程度まとまったお金ですしキリが良いので目標にしやすいからでしょう。
100万円はとても高額です。だからこそ100万円を貯め切れば達成感も味わえますし『貯金を成功させた』という自信にもなります。
ちなみに100万円を1年で貯めようと思うと1ヶ月当たり約84,000円を貯金に回す必要があります。
So-netが運営している情報サイト「マチエネ」のコラム『1カ月の貯蓄額の目安は、手取り月収の〇%!?』によると1ヶ月の貯蓄の目安は手取り月収の10~20%と言われています。つまり毎月84,000円を貯金に回そうと考えた場合、自身の手取り給料が最低でも40万円以上ないと難しくなります。
そもそも貯金において
『100万円を1年で貯めないといけない』
なんてルールはありませんので、毎月の貯蓄額を今の手取り月収の10~20%の間に決めて地道にコツコツ貯めていきましょう。100万円貯まるまで時間はかかりますが貯蓄額を守って取り組んだ方が“貯金する習慣”が身につくのでおすすめです。
生活費の3ヶ月分
・・・という人は今の生活費の3ヶ月分を貯金の目標金額に設定して貯金を始めてみてください。例えば
- 現在の生活費が15万円であれば目標貯金額は45万円
- 現在の生活費が20万円であれば目標貯金額は60万円
・・・といった感じです。100万円よりも目標のハードルが低いため半年から1年くらいで貯め切れるはずです。
貯金の目標として給料の3ヶ月を推奨するのは“万が一の生活費”として蓄えておくべき金額だからです。
例えば会社を退職したら失業保険が受け取れるのですが、自主退職の場合だと失業保険を申請してから実際に失業保険を受け取れるまでに3ヶ月の給付制限があります。この給付制限中に収入を得ると失業保険がもらえないため貯蓄で賄っていくしかありません。
そのため「貯金を始めるならまずは3ヶ月分の生活費を貯めましょう」と言われています。無事に3ヶ月分の生活費を貯め切れたら
・・・と少しずつ目標金額を吊り上げて貯金を続けていくのもアリです。
自分の年代の平均値・中央値を参考
自分と同じ年代の貯金額を参考に目標金額を決めるのもいいでしょう。各年代の貯蓄額の平均値は金融広報中央委員会が発表している『家計の金融行動に関する世論調査(2019年)』によると各年代の貯蓄額の平均値と固定値は以下の通りとなります。
| 年代別 | 平均値 | 中央値 |
| 20歳代 | 165万円 | 71万円 |
| 30歳代 | 529万円 | 240万円 |
| 40歳代 | 694万円 | 365万円 |
| 50歳代 | 1,194万円 | 600万円 |
| 60歳代 | 1,635万円 | 650万円 |
| 70歳以上 | 1,314万円 | 460万円 |
ただし、上記平均値は貯金以外にも株式、保険、投資信託といった資産も含まれた数字となっています。また貯蓄額が極端に高い人がいると平均値が上げられてしまうため平均値を参考に目標金額を決めるとハードルが高くなってしまいます。
貯金に対する自信がなかったり現在ほとんど貯金がないのであれば貯金の目標金額は平均値よりも固定値を参考にした方が良いでしょう。平均値と比べると中央値の方が数値は低いですから取り組みやすいと思います。
固定値とは?
中央値とはデータを小さい順(または大きい順)に並べた時に中央に来る値を指します。例えば
50万円、75万円、100万円、110万円、125万円、200万円、1,000万円
というデータがあった場合、上記データの中央値は真ん中にある『110万円』となります。一部のかけ離れた数値(上記のデータだと1,000万円)の影響がないため特定の地域の生活水準や年収を調べる際には平均値よりも中央値で判断する場合もあります。
欲しいものや買いたいものの値段
欲しい物や買いたい物がある場合、その購入金額を目標にすると貯金に対するモチベーションが高いまま維持できるのでオススメです。例えば
と思ったら買いたい車の価格を調べて
- いくらあれば買えるのか?
- どんな買い方があるのか?(ローンor一括支払)
- いつまでの買いたいのか?
を考えてみてください。すると自然と
- 毎月の貯金はいくらすればいいのか?
- どのくらい貯金を続ければいいのか?
がハッキリしてきます。
ただし車や住宅など高額なものを貯金で買おうとする場合、貯金に取り組む期間も長くなります。貯金の目標金額が100万円以上の時は短期間で結果を出そうとせず2~3年かけて気長に貯金に取り組む意識を持つと途中で挫折しにくくなると思います。
毎月貯金にまわす金額を決める

貯金を成功させるコツの中でも最も基本的なポイントが貯金に回す金額設定です。毎月貯金に回す金額設定を間違いさえしなければ継続して貯金が続けられます。
実際に貯金を継続して続けられる人の多くは、毎月の貯金額をあらかじめ決めてから節約や貯金に取り組んでいます。貯金に回す金額を決める際のポイントとしては次の3つを意識して決めると失敗する可能性は低くなりますので下記3点を意識してみてください。
月々の貯金額は固定
毎月貯金に回す金額については基本的に固定にします。具体的には
と決めたら、必ず2万円は貯金に回します。もし節約を頑張ってお金が余っても無理に貯金に回さず“自分が自由に使えるお金”として使い切ってしまって構いません。
貯金に回す金額を固定すれば
が計算しやすくなります。例えば毎月手取りが20万円の人が毎月2万円すると18万円で生活がやりくりできるよう考えればいいため、お金の使い方が習慣化されやすくなります。
収入が増えたり減ったりしたら貯金に回す金額も調整すればいいですが、月々の出費にあわせて貯金に回す金額を変えるのは良くありません。貯金を成功させるには月々の貯金額は固定するようにしましょう。
月々の貯金額は“多すぎず”“少なすぎず”
月々の貯金額を毎月固定させるうえで大事になるのが『月々の貯金額をいくらにするのか?』です。貯金額が多すぎすると生活に支障が出てしまいますし少なすぎると一向に貯金が貯まりませんからね。
月々の貯金額は多すぎず・少なすぎずの適切な金額に設定しましょう。目安としては手取り月収の15%前後がベストだと言われています。
金融広報中央委員会が発表した「家計の金融行動に関する世論調査(令和元年)」によると手取り収入における貯蓄の割合で最も多いのが10~15%という結果になりました。
| 給料に対する貯蓄割合 | 単体世帯 | 二人以上世帯 |
| 5%未満 | 5.8% | 8.1% |
| 5~10% | 11.2% | 15.1% |
| 10~15% | 15.2% | 18.9% |
| 15~20% | 4.1% | 4.7% |
| 20~25% | 8.5% | 7.0% |
| 25~30% | 2.3% | 1.3% |
| 30~35% | 6.8% | 2.7% |
| 35%以上 | 9.5% | 2.5% |
| 貯蓄しなかった | 36.6% | 32.6% |
もちろん収入が多ければ貯金に回す金額の割合を15%以上にしても生活できるでしょう。しかし“貯金に回す金額が多くなる=自由に使えるお金が少なくなる”となり、お金の使い方に制約が生じてストレスを溜めこむ可能性もゼロではありません。
特に今まで何度も貯金を始めては挫折してしまった人は、貯金を始めてしばらくは手取り月収の10~15%くらいに設定して貯金をスタートさせましょう。無理のない金額を貯金し続ければ“貯金をする”という習慣がつく上に
という自信がつきますからね。
給料が入ってすぐに貯金分だけ引き出す
毎月貯金に回す金額を決めたら、必ず貯金する分のお金は別の専用口座などに移して普段使うお金とは違うところに保管しておきましょう。この時貯金するお金は“給料が入った日”にすぐ移動させるのがポイント。
いわゆる“先取り貯蓄”という方法で、貯金を継続して取り組んでいる人の多くは先取り貯蓄を採用しています。
人はお金を持っていたら持っていた分だけ使ってしまう習慣があります。これを「パーキンソンの法則」と言います。
パーキンソンの法則とは?
パーキンソンの法則とは、もともとは「役人の組織は、実際に必要な仕事の量に関係なく肥大化する傾向がある」というもの。そこから「人間は与えられた分の時間やお金をすべて使い切る傾向があり、時間やお金の拡大は最終的に組織を腐敗させる」ことを意味する。
パーキンソンの法則は、以下で構成される。
第1法則:仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する
第2法則:支出の額は、収入の額に達するまで膨張する
第3法則:拡大は複雑化を意味し、組織を腐敗させる
凡俗法則:組織はどうでもいい物事に対して、不釣り合いなほど重点を置くイギリスの歴史学者で政治学者のシリル・ノースコート・パーキンソンが『パーキンソンの法則:進歩の追求』で提唱した。イギリスの官僚組織の研究から生み出された法則。
引用:シマウマ用語集
お金を持っていたら使ってしまいたい気持ちは人間の心理なので抵抗するのはとても大変です。だから貯金に回す分のお金をあらかじめ“なかったこと”にすれば仮に残ったお金を全額使い切っても貯金分のお金は無傷で済みます。
ただし、いくら貯金を別の口座に移しても貯金用の口座から簡単に引き出せるようでは意味がありません。
貯めたお金を気軽に引き出せないように
- 貯金用の口座を定期預金口座にする
- 貯金用口座のキャッシュカードは財布に入れない
などといった工夫をすると無理なく貯金が貯められます。
収支を見直して簡単なところから節約
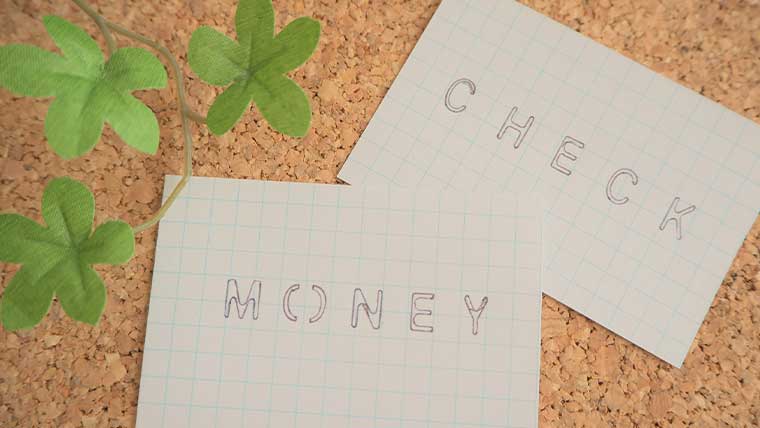
貯金を成功させるためには貯金に回すお金をねん出しなければいけません。貯金に回すお金を作るためには収支を見直して支出を節約するのがもっとも効果的な方法です。
支出の見直しや節約はいきなり全ての支出を同時に始めるとワケが分からなくなってしまい、途中で挫折してしまいます。特に生活費の見直しや節約は支出項目もたくさんありますので“簡単に節約できる支出”から見直して節約に取り組んでいきましょう。
具体的には
- 固定費
- 食費
- その他の支出
の順番に見直すのがおすすめです。
固定費の見直し・節約
生活費を見直すのであれば固定費から見直し、節約に取り組むのが成功のコツです。なぜなら固定費の見直しや節約は変動費(特に食費)と比べて簡単だからです。
例えば今住んでいる住まいの家賃が8万円だったとしましょう。その住まいから家賃6万円のところに引っ越せば毎月2万円の節約に成功しているのと同じ意味になります。
固定費の多くは契約しているプランや利用方法を見直し、新しいプランに乗り換えることで節約できます。もちろん使い方の改善も必要ですが使い方の改善に伴うストレスも食費に比べると少ないので生活費を見直したり節約を始めるのであれば固定費から見直しましょう。
具体的には以下の3つの支出の見直しから始めるのをお勧めします。
通信費
総務省統計局によると二人以上の世帯の通信費の平均は13,201円となっています。(引用:総務省統計局『家計消費状況調査年報 平成30年』より)節約を徹底している家庭であれば夫婦2人で通信費を10,000円以下にしているところもあります。
通信費の見直し方は簡単です。現在契約しているプランを確認して利用料金を調べるとともに、他社や他のプランと比較して
を考えるだけ。
スマホも格安SIMなどの登場によって月々2~3000円で利用できるプランがあったりします。またインターネットもパソコンやスマホの普及に伴ってより使いやすく格安なプランが登場しています。
さらに時期によっては乗り換えや新規契約でキャッシュバックがもらえるキャンペーンを開催している通信会社もあります。徹底的に通信費を節約している人の中にはキャッシュバックキャンペーンを上手に利用して通信費をギリギリまで抑えていたりもします。
具体的な通信費の節約方法については下記ページで紹介しています。個人的にも通信費は簡単に見直しができるうえに節約効果も高いので優先的に節約に取り組むのをお勧めします。
光熱費
電気代、水道代、ガス代といった光熱費も優先的に支出を見直して節約に取り組むのをお勧めします。総務省統計局によると光熱費の平均支出は以下のようになっています。
| 光熱費の支出項目 | 平均金額 |
| 電気代 | 9,151円 |
| ガス代 | 4,216円 |
| 水道代 | 4,131円 |
| その他光熱費 | 1,179円 |
| 合計 | 18,677円 |
光熱費を節約するコツは自宅の過ごし方を見直すことです。
例えば
- 部屋を出る時電気の消し忘れはないか?
- 水を流しっぱなしにする時間は長くないか?
- 待機電力を消費している状態になっていないか?
- 使わない家電は主電源から切っているか?
などなど。1つ1つの行動に対する節約効果は決して大きくありませんが光熱費の無駄遣いをしない生活が習慣化できれば節約を意識しなくても支出が抑えられるようになります。
また近年電気代に至っては“電力自由化”によって電力会社や契約プランを見直して節約している人も増えてきました。
電力会社を乗り換えるとそもそもの電気料金(基本料金や利用料金など)が変わります。つまり今までと同じ電気の使い方をしても電気代が節約できるのです。
電力会社の選び方については下記ページでポイントを紹介しています。電力会社は住んでいる地域などで選べる会社や選択数が変わってくるのでしっかりとポイントを押さえて比較しましょう。
保険料
固定費の中でも住宅費の次に高いのが保険料です。
公益財団法人生命保険文化センターの調べによると平成30年度の生命保険の年間払込金額の平均は381,700円となっています。つまり毎月の生命保険料の平均は約31,800円となります。
保険は一度契約すると解約するまで払い続ける支出のため
を定期的に見直すのが節約のコツです。
保険は保障内容の手厚さに比例して保険料が高くなります。あれもこれも・・・と保障を厚くすると保険料が高くなり生活費を圧迫するので必要最低限の保障だけカバーできる保険に切り替えましょう。
とはいえ
・・・を自分で判断できる人は多くないでしょう。もし自分で加入すべき保険が分からないのであれば“保険相談サービス”を利用してみてください。
保険相談サービスはショッピングモールなどに店舗を構えているところもあれば、自宅や職場の近くまで来てくれる派遣型のところもあります。保険相談サービスの選び方については下記ページで解説しているので保険相談サービス会社の選び方の参考にしてください。
食費の見直し・節約
生活費の中で気を緩めると膨らみがちなのが食費です。
食費は世帯人数によって食費にかけるべき支出の割合も変わってくるため、食費を見直す際は“エンゲル係数”を頭に入れて比較するといいでしょう。
エンゲル係数とは『毎月の支出のうち食費にかける適切な割合』を示す数字です。
総務省統計局が発表している家計調査によると、エンゲル係数の平均は約25%となっているため、食費を生活費の25%以内に抑えられれば十分だと判断できます。
ちなみにエンゲル係数の計算方法は以下の通りです。
エンゲル係数(%) = 食費÷消費支出×100
もしご自分の生活費のエンゲル係数を計算して25%を超えている場合は食費にお金をかけすぎている可能性が高いため積極的に節約を実践しましょう。食費を節約するコツとしては次の3点がポイントです。
自炊を心がける
食費が高い原因としてよく挙げられるのは“自炊の回数が少ない”点です。外食で済ましたり惣菜や弁当を買って食べるとどうしても食費がかさんでしまいますので積極的に自炊するよう心がけましょう。
例えば昼食に必ず500円の弁当を買えば月間で15,000円かかる計算になります。しかし弁当を家から持参すれば15,000円の出費はなくなりますよね?
自炊に関しては料理の得意・不得意があります。特に自炊が苦手な人は
- 献立が決められない
- 料理の腕に自信がない
- 自炊が長続きしない
などといった悩みを抱えていると思います。そんな人のために下記ページで食費節約につながる献立の立て方を紹介しているのでぜひ参考にしてください。
コンビニに立ち寄らない
食費を節約するのであればコンビニでの買い物は極力避けましょう。コンビニは品ぞろえが良いうえに営業時間が長いためついつい利用しがちですが
- 欲しい物以外の商品まで買ってしまいがち
- 売っている商品がスーパーに比べて割高
といったデメリットがあります。食費を節約するのであれば『コンビニに頼らない買い物の仕方』を確立させる必要があるため、コンビニは使わないように心がけましょう。
外食をなるべく控える
食費の節約をするなら自炊する回数を増やすとともに外食の回数を減らしていきましょう。
例えば毎週末飲みに出ていたのを月に1回に減らせば1ヶ月の飲み代は1/4に減らせますよね?仮に1回の飲み会が5,000円だとするならば15,000円の節約になります。
ただし、仕事の都合や家族サービスなどで外食をする機会もあると思います。
といって外食を完全に断つのではなくきちんと毎月予算を組んで“外食に使えるお金”を用意しておくといいでしょう。外食に使う予算については総務省統計局が発表している家計調査の平均を参考にしてください。
- 単体世帯:10,653円
- 二人以上の世帯:12,247円
その他支出の見直し・節約
固定費や食費以外の支出についても見直す必要があります。特に
- 趣味・娯楽に使うお金
- 服・日用雑貨を買うお金
については支出として必要ではあるものの、ついつい衝動買いをしてしまう人も少なくないと思います。家計再生コンサルタントの横山光昭さんによると上記2つの支出割合は
- 趣味・娯楽費は手取り月収の2~3%
- 被服費・日用雑貨費は手取り月収の5~6%
ぐらいに収めると良いと言われています。どちらの支出も気が緩むと修道買いや無駄遣いをしてしまう危険性が高いため、きちんと予算を組んでやりくりするよう心がけてください。
趣味・娯楽費
趣味や娯楽にお金は気が緩むとついつい使いすぎてしまう人も少なくありません。貯金を貯めるためには欲しいものを買うガマンも節約を通して身につけるといいでしょう。
ただし趣味な娯楽に使うお金を“ゼロ”にするのもお勧めしません。
節約のために抑えがちな趣味・娯楽費ですがゼロにすると日々のストレスが発散できず生活に支障が出る危険性があります。趣味や娯楽費を見直して節約をするのであれば“お金の使い方”に対する考え方を変えて取り組むようにしましょう。
被服費・日用雑貨購入費
服や日用雑貨は生活に必要な物ですが毎月買う必要はありません。月々日用品や服を買う予算は使わずに取ってはおき、いざ買う時になったら今まで取っておいたお金を使うようにしましょう。
特に服は季節に1回とか半年に1回のペースでも十分間に合います。
・・・というタイミングで服を買っても十分間に合うので服の買い替えの頻度はできるだけ増やさないよう注意してください。
“無駄遣い対策”を考えて実践する

貯金を貯めるために生活費を見直して節約に取り組むのも大事ですが、もっと大事なのが“無駄遣いを減らす”対策です。
無駄遣いが増えれば貯金に回すためのお金がどんどん減っていきます。日ごろのお金の使い方や買い物の仕方を振り返り
・・・というものがあれば、今後同じ無駄遣いをしないよう買い物の仕方を意識してください。具体的に次の4点を意識すると無駄遣いが減らせます。
クレジットカードで買い物はしない
クレジットカードはお金がなくても買い物ができる便利なアイテムです。しかしクレジットカードで買い物した分のお金は後日カード会社からまとめて請求されるため
・・・というのが把握できない人はクレジットカードでの買い物はしないようしましょう。
特にクレジットカードのリボ払いは絶対に利用しないように!
リボ払いにすれば月々の支払い額は減りますが、利用金額がゼロになるまで支払い続けなければいけません。さらに利用金額に“金利”が上乗せされた額を支払う必要があるため、結果的に割高な金額で買い物をしたことになります。
クレジットカードの正しい利用方法は下記ページで紹介しています。クレジットカードを使うのは良いですが慣れないうちは無駄遣いを引き起こしかねないのでできるだけ利用は控えましょう。
ローンは組まない
貯金を貯めたいのであればできるだけローンを組むのは控えましょう。ローンを組むと購入金額とは別に金利も支払う必要があるからです。
新居や車など何百万円もの買い物をする場合はローンを組んで購入するのが一般的なのでローンでの購入を考えてもいいでしょう。しかし車と新居以外の物を買う場合は金利を支払うのが無駄なので一括で買うようにしましょう。
一括で買うのが難しい場合は、コツコツお金を貯めてから買うように。
という気持ちで取り組むと貯金に対するモチベーションにもなります。
「買う」と決めるのは2回目以降の来店で
欲しいものがあった場合、一度目の来店で購入を決断しないクセをつけましょう。1度目の来店で価格を確認し、その後帰宅してから
- 買っても生活費に支障は出ないか?
- 本当に今必要なのか?
などを冷静な気持ちで吟味してください。またインターネットなどで検索して
・・・を調べると欲しいものをより安く買えたりします。「欲しい!買いたい!」という気持ちに任せて買ってしまうと後日後悔する可能性もありますので、即決で購入を判断しないのが無駄遣いを減らすコツです。
「つもり貯金」で貯金する
無駄遣いを減らす具体的な方法として「つもり貯金」があります。
つもり貯金とは“〇〇を買った”というつもりになって貯金箱にお金を入れる貯金法です。例えば
- お菓子を買ったつもりで500円を貯金する
- 服を買ったつもりになって5,000円を貯金する
・・・といった感じ。
つもり貯金は特に衝動買いが多い人におすすめ。衝動買いしたい気分を緩和できるうえに無駄遣いの抑制にもつながります。
また食費や娯楽費などつもり貯金で貯めたお金の出所が“生活費”として予算を組んでいるお金であれば、貯めたお金は自由に使って構いません。
例えば
- 毎日の缶コーヒーを我慢して貯めたお金で週末ケーキを買う
- 弁当を買うお金をつもり貯金で貯めて飲み代にする
などなど。基本的に生活費として考えているお金は全額使い切って問題ないので、つもり貯金で貯めたお金は自由に使ってしまいましょう。
家計簿をつけて記録に残す

貯金を成功させるコツとして“家計簿をつける”は基本です。
家計簿をつけることで日々のお金の使い方が確認できるため、使いすぎの支出や無駄遣いを見つけやすくなります。貯金や節約を始める際には自身のお金の使い方を振り返るためにも家計簿をつけるのをおすすめします。
家計簿をつける際に重要なのは支出だけではなく“貯めたお金”も記録しておくこと。
収入や支出だけでなく “貯めたお金”も家計簿に記入すると貯金額に意識が向けられるため
・・・という気持ちが家計簿を見るたびに強くなります。
この家計簿に貯金の記録をつけるのは「レコーディングダイエット」の応用でもあります。
レコーディングダイエットとは岡田斗司夫さんの著書『いつまでもデブと思うなよ』で紹介されたダイエット法。食べたものや摂取カロリーを記録して日々の食生活や摂取カロリーを記録することで自身が摂取しているカロリーや食事の内容を自覚し、食生活の改善につなげる効果があります。
貯金も同じで家計簿で累計の貯金額を記載するだけで貯金に対するモチベーションが高くなります。家計簿のつけ方については下記ページで紹介しているのでぜひ参考にしてください。
制度を活用して“節税”
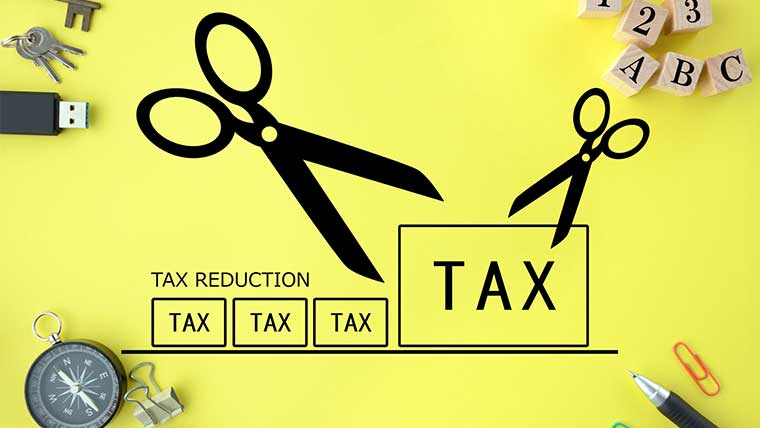
貯金を貯めるためには“出ていくお金”を少しでも減らす行動が必須です。多くの人は食費などの生活費だったり趣味や遊びに使うお金を減らそうと考えますが“税金の節約”についてはあまり考えている人は少ないのではないでしょうか?
節税は自営業や会社経営者だけでなく会社員でもできます。節税に取り組めば“出ていくお金”が減らせるので貯金のためにも節税について勉強し、できるものから積極的に初めて行きましょう。
節税の具体的な方法については以下の4つの制度の活用が一般的です。
所得控除
所得控除とは一定の条件に当てはまる場合に、所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度を指します。税金は所得を元に計算されるため所得が低くなれば納税額も少なくなります。
所得控除には色々な種類があります。例えば会社員であれば以下のような所得控除が受けられます。
| 控除の種類 | 控除が受けられる条件 |
| 基礎控除 | 誰でも受けられる控除 |
| 配偶者控除 | 納税者本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除 |
| 扶養控除 | 納税者本人に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる控除 |
| 障害者控除 | 納税者本人もしくは控除対象配偶者や扶養家族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる控除 |
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領などで納税者・納税者と生計を同じくする親族の資産が損害を受けた場合に受けられる控除 |
| 医療費控除 | 納税者・納税者と生計を同じくする親族が医療費を支払った場合に受けられる控除 |
| 社会保険料控除 | 納税者・納税者と生計を同じくする親族が社会保険料を支払った際に受けられる控除 |
| 勤労学生控除 | 納税者が所得税法上の勤労学生である場合に受けられる控除 |
| 寡婦・寡夫控除 | 納税者が離婚したり配偶者と死別などによって寡婦(寡夫)になった場合に受けられる控除 |
| 生命保険料控除 | 納税者が保険料(生命保険、介護医療保険、個人年金保険)を支払った際に受けられる控除 |
| 地震保険料保険 | 納税者が地震保険料を支払った際に受けられる控除 |
| 寄附金控除 | 国、自治体、特定公益増進法人などに寄附をすると受けられる控除 |
※各所得控除には控除を受けられる条件があります。各控除が受けられる条件については下記参考サイトをご参照ください。
控除を受ける際には勤務先で年末調整をするだけで問題ありません。ただし
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄付金控除
については確定申告をする必要になりますので、上記3つの控除を受ける際には確定申告をするようにしましょう。
ふるさと納税
ふるさと納税とは好きな自治体に寄附ができる制度を指します。寄附金は原則自由ですが2,000円を超える金額を寄附した場合、超過金額分が所得税で還付されたり住民税の控除額となります。
例えばふるさと納税で10,000円分寄付したとすると8,000円が“寄付金控除”となる計算です。
さらにふるさと納税によって寄附すると寄附した自治体から特産品(返礼品)が送られてきます。そのため『実質2,000円で各地の名産品が買える』ということでふるさと納税を積極的に利用している人は年々増えています。
ふるさと納税をした際の控除を受けるには確定申告が必要になります。会社員でも確定申告をしないと寄付金控除は受けられないのでふるさと納税をした際には確定申告を忘れないように。
iDeco(イデコ)
iDeco(イデコ・個人型確定拠出年金)とは老後の資金を貯めるための制度を指します。掛け金は5,000円から始められて60歳になったら受け取れるようになります。
iDecoに加入すると年間の掛け金が所得控除の対象となります。例えば毎月1万円ずつiDecoに積み立てた場合、12万円が控除されます。
またiDecoで積み立てたお金は『定期預金』『保険』『投資信託』と3つの中から使い道を選べます。この時『投資信託』を選択して運用益が発生しても運用益に対する税金が安くなります。
ただしiDecoのデメリットとして
- 60歳にならないと積み立てたお金は使えない
- iDeco専用の口座を開設する必要がある(手数料が発生)
- お金を受け取るタイミングで税金がかかる
があります。納める税金を抑えつつ老後のための貯金を貯める方法と考えるのであればiDecoは有効な手段だと思いますので検討してみてはいかがでしょう。
つみたてNISA
つみたてNISAとは投資によって発生した利益に対する税金がかからない投資専用口座のこと。非課税期間は投資を始めた年から最長20年間継続されます。
つみたてNISAは毎月先行口座に一定金額を積み立てていきます。その点はiDecoと変わりませんが、iDecoと違って運用資産の引き出しに条件がなくいつでも引き出せます。
ただし所得控除が受けられるiDecoとは違い、つみたてNISAは所得控除が受けられません。あくまでも“投資での運用益による課税がかからない”のがつみたてNISAの特徴です。
つみたてNISAは投資信託による投資をするための口座です。しかもつみたてNISAで購入できる金融商品は金融庁から許可を得た173本(2019年10月時点)に限定されているため投資初心者向きの投資口座と言えるでしょう。
時間を見つけて副業に取り組む

貯金を貯めるには収入が必要です。しかも生活費を差し引いても残っているだけの収入がないと貯金はできません。
収入は人によって違います。もし現在収入が少なく生活費だけでカツカツ・・・という人は副業を始めて“収入を増やす”という選択肢も考えて行動をした方が良いでしょう。
副業は年齢や性別によって選択肢が変わってきます。具体的には
- 学生
- 主婦
- 会社員
では副業を選ぶ基準や副業で得られる金額も変わります。
学生におすすめの副業
学生におすすめの副業・・・といっても基本的に学生ができる副業はアルバイトになります。
高校生以下だと学校や年齢によってはアルバイトができません。しかし大学生になれば自由な時間も多く年齢的にアルバイトできる業種も増えるため選択肢は多岐にわたります。
とはいえ学生は“学業”がメインなので学校生活を疎かにするような仕事はしないように。アルバイト探しは「バイトル」や「タウンワーク」などといったバイト情報サイトを参考に
- 空いている時間にできる仕事
- 自分が興味のある仕事
- 自宅から通える勤務地
をポイントにして探すといいでしょう。
主婦におすすめの副業
主婦の場合、小さいお子さんがいる・いないによって選べる副業の選択肢が変わってきます。
お子さんがいない場合はパートで外に働きに出ることも可能ですが、小さいお子さんがいるとなかなかパートで外に働きに行くのも難しかったりします。そんな家を空けづらい主婦には“在宅ワーク”を中心に副業を始めるのがおすすめ。
在宅ワークも近年色々な仕事が増えてきました。下記ページで主婦におすすめの在宅ワークを紹介していますので参考にしてください。
会社員におすすめの副業
会社員の場合、平日の昼間は本業があるため副業が取り組める時間帯は仕事が終わった後か休日のみと副業ができる時間が限られます。ダブルワークもいいですが本業に支障が出る可能性もゼロではないので“無理をしなくてもいい副業”がおすすめ。
具体的には在宅ワークを中心とした自宅でできる副業がいいでしょう。クラウドソーシングやポイントサイトなどは手軽にできる副業なのでおすすめです。
またアフィリエイトやブログを開設して広告収入を得るのも会社員の副業としておすすめです。収入が発生するまで時間はかかりますが軌道に乗れば本業以上の収入が期待できます。
上記以外のおすすめ副業については下記ページで紹介しています。この中から興味があったりできそうな副業があれば始めてみてはいかがでしょう。
まとめ
貯金を貯めるにはしっかりと“コツ”を押さえた考えと行動が必要になります。コツを押さえて貯金に取り組まない限りお金は一向に貯まっていかないでしょう。
とはいっても、貯金コツは決して難しいものではありません。コツさえしっかり押さえて取り組めば低収入であってもコツコツお金を貯め続けられます。
これまで貯金を始めても挫折してしまった人はぜひ当ページで紹介した貯金を貯めるためのコツを習慣づけるところから始めてみてください。
・・・というところから始めて少しずつ“貯金ができる人”になっていきましょう。