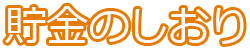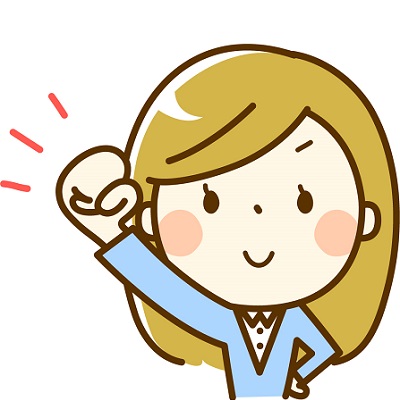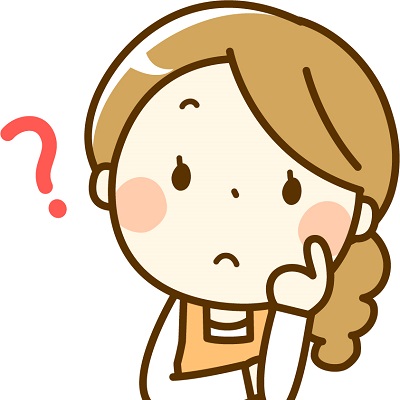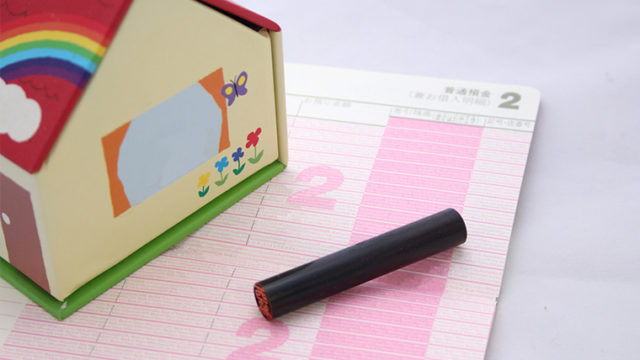先日妹が女の子を出産しました。子供もいなければ結婚もしていない生き遅れた兄貴ですがふと「教育費」について考えてしまったわけで。
僕も妹も大学まで行かせてもらったわけですが、いったい親がどのくらいのお金を用意してくれたのか?については特に考えたことがありませんでした。しかし姪っ子について親や妹とお金の話をきっかけに子どもの養育費の平均がどのくらいか気になったため、調べてみました。
また教育費を貯める方法についてもいくつかご提案しています。皮算用な部分もあるかもしれませんが参考になればうれしいです。
目次
「私立」と「公立」で教育費が変わってくる

教育費がいくら必要か?については子供を“公立”にいかせるか“私立”に行かせるか?で大きく変わってきます。ちなみに公立と私立との違いは以下の通りです。
公立・・・国や自治体が運営している
私立・・・民間団体や私人が運営している
幼稚園・保育園から大学まで私立と公立とに分かれています。もちろん公立と私立とではかかるお金が違います。
文部科学省が発表した平成28年度子供の学習費調査によると、公立と私立の1年間の学習費総額の違いは以下の通りです。
| 公立 | 私立 | |
| 幼稚園 | 23万4千円 | 48万2千円 |
| 小学校 | 32万2千円 | 152万8千円 |
| 中学校 | 47万9千円 | 132万7千円 |
| 高校(全日制) | 45万1千円 | 104万円 |
引用:文部科学省「子供の学習費調査‐平成28年度子供の学習費調査」
※上記数字は学校授業料以外にも給食費や部活動費も含まれています。
誤解があるといけないので繰り返しますが上記はあくまでも『1年間でかかる教育費』の平均です。
学年によって学校教育費も変わるものの、上記金額を元に通う年数をかけて総額を計算すると以下のようになります。
| 公立 | 私立 | |
| 幼稚園(3年) | 70万2千円 | 144万6千円 |
| 小学校(6年) | 193万2千円 | 916万8千円 |
| 中学校(3年) | 143万7千円 | 398万1千円 |
| 高校(3年全日制) | 135万3千円 | 312万円 |
| 合計 | 542万4千円 | 1,771万5千円 |
つまり、幼稚園から高校までオール公立に通わせるのとオール私立で通わせるのとでは約1,200万円以上もの違いが出てきます。さらに塾などの学校外教育費も考慮すると年間の教育費はさらに増えます。
子供がどの学校に進学するかはその時になってみないと分かりませんが
という教育熱心な親御さんは最低でも教育費で1,700万円は絶対にかかると思った方がいいでしょう。
教育費で最もお金がかかるのは「大学」

先ほど幼稚園から高校までの教育費の平均を公立と私立とで分けて紹介しました。しかし教育費で最も考えるべきところは「大学」の学費です。
大学も公立と私立で必要な学費が変わってきます。さらに大学は“学部”によっても必要な教育費が違います。
例えば文系の学部と理系の学部とで学費(特に授業料)は変わります。中でも医学部や歯学部は入学金も授業料もかなりかかるため、子供を医者にしたい人は教育費の準備も早い段階から始めた方がいいでしょう。
具体的に大学にかかる費用については以下の通りです。
国公立大学
| 入学金 | 28.2万円 |
| 授業料 | 53.6万円 |
| 施設・設備費 | |
| 4年合計 | 242.6万円 |
私立大学(文系)
| 入学金 | 23.5万円 |
| 授業料 | 75.9万 |
| 施設・設備費 | 15.7万円 |
| 4年合計 | 389.9万円 |
私立大学(理系)
| 入学金 | 25.6万円 |
| 授業料 | 107.2万円 |
| 施設・設備費 | 19.1万円 |
| 4年合計 | 530.8万円 |
私立大学(医歯学部)
| 入学金 | 101.3万円 |
| 授業料 | 289.7万円 |
| 施設・設備費 | 88.3万円 |
| 4年合計 | 2369.3万円 |
大学の場合、私立に比べて国公立の方が入学のハードルが高いため
と考えるのであれば私立大学を想定して教育費を貯めておいた方がいいでしょう。つまり子供が18になったら教育費として400万~500万円はかかる・・・と見越してお金の計画をするのが良いと思います。
親元から離れて大学に通うケースもある
高校までであれば、よほどレアなケースでない限り実家から通える範囲の学校を進学先に選ぶと思います。しかし大学になると選択肢が全国に広がるため、親元から離れて一人暮らしをするケースも珍しくありません。
となると、一人暮らしの費用も当然教育費としてかかってきます。大学によっては寮など下宿先を用意しているところもあって、ある程度下宿代を安くできたりもしますが大学の授業料にプラスアルファで費用が掛かるのは間違いありません。
もっとも、子供がどこの大学に行くのか?はその時になってみないと分かりません。また大学生になればアルバイトもできるので生活費を全額親が負担する必要もないですが、場合によっては大学にかかる必要が増える可能性がある点だけは意識しておくといいかもしれません。
教育費をいくら貯めると安心か?

これまで幼稚園に入れてから大学を卒業するまでの教育費をざっと計算した結果を紹介しました。幼稚園から大学まですべて公立に行かせたとしてもだいたい800万円くらいかかりますし、私立に行かせるとさらに教育費は増える可能性があります。
・・・と不安に思う人いるかもしれませんがご安心ください。教育費を全額貯蓄に頼る必要はありません。
そもそも教育費でまとまったお金が必要なのは進学した時の入学金くらい。授業料についてはその時の家計をやりくりしたりすれば教育費用の貯金が少なくてもなんとかなります。
もちろん子供を早い段階から私立に行かせるのであれば、家計のやりくりだけでは厳しいかもしれません。特に小学校から私立に行かせようとすると公立の小学校よりも学費が年間100万円以上の違いが出ますからね。
しかし
という考えであれば、教育費はそこまで大きな負担にはなりません。月々の支出から“教育費”として支払っても公立であればやりくりできる金額なので必死に教育費のための貯金を貯めなくても大丈夫だと思います。
ただし、子供の将来のためにある程度進学先の可能性を広げるためにも教育費に使うための貯金はしておいて損はありません。一般的に教育費で600万円くらい貯金があれば大丈夫と言われているので、とりあえず『600万円』を目標貯金額として定めておくといいでしょう。
無理なく教育費を貯める方法

先ほど教育費のための貯金額を『600万円』にしておきましょう・・・・とお話ししました。とはいっても600万円って結構大きな金額ですよね?
と悩んでいる人も多いと思います。そんな人のために、個人的に“無理なく貯蓄するための行動”をいくつかご提案します。
これから紹介する方法を全て実践する必要はありませんが、できそうなものがあれば今すぐ行動に移すと貯金の成功確率も高くなるのでぜひ実践してみてください。
なるべく早く教育の貯蓄を始める
いきなり600万円もの大金を作るのはよほど収入がないと不可能です。おそらく2~3年で600万円ものお金を貯められる家庭はほとんどいないでしょう。
教育費は子供が生まれたら全額すぐに必要なわけではありません。特に貯金を使うのは大学の学費がメインとなってくるため、10~15年くらいかけて長期的に貯めていく計画を夫婦で考えて取り組んでいきましょう。
仮に『15年で600万円貯める』と計画した場合、年間で40万円ずつ貯蓄していけばいいですし、月間にすると約3~4万円貯金に回せばいい計算になります。このくらいであれば無理なくできるのではないでしょうか?
共働きできる時に多めに貯めておく
教育費は別に子供が生まれてから貯め始める必要はありません。むしろ子供ができる前から先駆けて準備しておくとあとあと楽になります。
特に結婚してから子供ができるまでの期間は夫婦共働きができます。つまり家計の収入が増やせる機会ですし、子供がいない分支出も抑えられるのでもっとも貯金がしやすい時期と言われています。
子供を望んでいるのなら、なるべく早めに教育費の貯金はしておくよう夫婦でお金の使い道などを話しておきましょう。
学資保険でカバーする
教育費を貯めておく方法の1つが『学資保険』の利用です。学資保険とは子供にかける教育費を準備する目的で販売されている保険で、進学時の祝い金や満期保険金が受け取れます。
貯蓄が苦手な人は学資保険で教育費を貯めておくのもいいでしょう。保険という形で教育費を貯めておけるため、教育費を間違って使い込む・・・なんてことが起こりません。
学資保険に加入するかどうか?は夫婦の保険を見直す時に併せて考えればいいと思います。
資産運用で教育費を作るのもアリ
教育費を作る方法として昔から利用されている学資保険ですが、最近は保険以外にも教育費を作る方法があります。特に気になるのが“資産運用”の一環で教育費を作る方法です。
例えば「ジュニアNISA」とか。
ジュニアNISAとは0歳~19歳の未成年が利用できるNISAで、口座を開設して資産運用によって得られた利益のうち年間80万円までは非課税になる制度のこと。非課税の期間は最長5年まで伸ばせるため、実質最大400万円までの利益が非課税となります。
ジュニアNISAは「子どもの将来に向けた資産形成をサポートするため」に導入された制度のため大学にかかる費用を中心に資産運用で作っていけます。ただしデメリットとして
- ジュニアNISAが利用できる期間は2023年まで
- 18歳にならないと口座の資金が引き出せない
- 口座にある資産が目減りするリスクがある
などがあります。ただ子供の教育費を作るために資産運用をする・・・という方法はアリだと個人的には思うので、教育費を作るのをきっかけに資産運用について勉強してみてもいいかもしれません。
自治体からもらえる手当てを貯金に回す
各自治体によって子供を出産した場合にもらえる手当てがあります。手当の種類や金額については自治体によって異なりますので、妊娠が分かったら自治体に一度相談に行ってみましょう。
手当の使い道については各家庭によって違うと思います。
例えばうちの母は手当でもらった額をそのまま学資保険に回していた・・・と言っていました。もちろん手当てをそのまま貯金して現金として貯蓄するのもアリだと思います。
最悪なのは手当の存在を知らずもらいそびれることです。基本的にどの自治体にも出産手当はあると思いますので、申請の仕方やタイミングは事前に調べておきましょう。
家計の収入を増やす
ある程度子供が大きくなれば幼稚園や保育園に預けられますが、その年になるまでは家で育児をしなければいけません。しかし幼稚園等に預けられるまで“共働き”ができないか?というとそんなことはありません。
特に最近は自宅で仕事ができる『在宅ワーク』が増えています。
正社員の給料に比べるとどうしても少なく感じてしまうかもしれませんが、自宅でできますし空いた時間に取り組めてお金が稼げますので、育児をしながらでも仕事ができます。
在宅ワークでできる仕事は多種にわたります。資格やスキルが求められるものもありますが、なくてもできるカンタンな仕事もありますので育児をメインに空いた時間に取り組むと家計の収入を増やせるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?あくまでも個人的に調べた結果なので参考程度にしかならないと思いますが教育費として貯めておくのなら学費の平均などから『600万円』を1つの目標にして貯金に取り組まれるといいでしょう。
家計の収入によって600万円のハードルは変わってきます。後半部分でお話しした教育費を貯める方法
- 早めに貯金を始める
- 学資保険を活用する
- 出産における手当は忘れず受け取る
- 少しでも収入を増やす
はできるところから始めてみください。スタートが早ければ早いほど教育費の不安は解消されますからね。