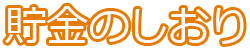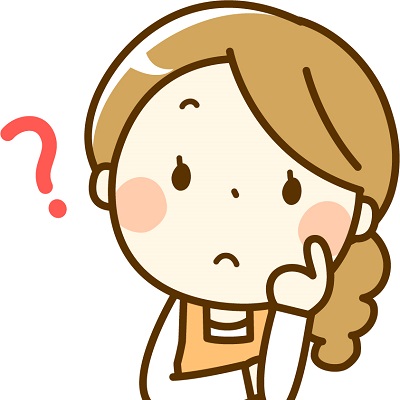生活費を節約したいのであれば光熱費の見直しは欠かせません。その中の1つ『水道代』の節約について紹介していきます。
水道代は1ヶ月に数千円くらいかかります。他の生活費の月間支出と比べると決して多くはありません・・・が
という人も少なくないはず。
水道代を節約する方法としては色々な手段があります。中でも“お手軽”にできる節水方法を4つ紹介しますので早速取り入れてみてください。
目次
水道料金の仕組みについて理解する
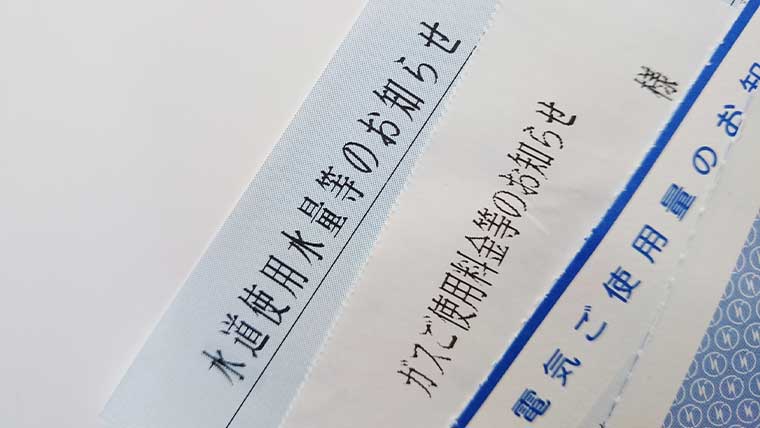
水道代を節約するにはまず水道代がどのように決まっているか?を理解しておくことが大切です。水道代の仕組みを理解しておくと無意味は節水方法をしなくてもよくなりますからね。
水道代は以下の計算式によって算出されます。
(基本料金+従量料金+下水道料金)×消費税
実は水道代の基本料金も従量料金も通話料や電気代と少し計算方法が違います。各料金の計算方法については以下の通りです。
水道代の基本料金の計算方法
水道を使う場合、地域を管轄する水道局と契約する必要があります。基本料金は“水道を使用する権利”を購入する料金で毎月必ず発生する料金です。
基本料金は利用する水道の口径によって変わってきます。例えば東京水道局が管轄するエリアの基本料金は以下のようになっています。
| 口径サイズ | 基本料金 |
| 13mm | 860円 |
| 20mm | 1,170円 |
| 25mm | 1,460円 |
| 30mm | 3,435円 |
| 40mm | 6,865円 |
出典:東京水道局
一般家庭の場合口径は13mmもしくは20mmが主流です。
・・・と気になった人は水道の検針票に記載されていますのでそちらを確認すればすぐに分かります。
口径の大きさによる違いは一度に使える水量です。例えばお風呂にお湯を溜めながらキッチンで水を使おうとすると13mm口径だと水圧が低下する可能性があります。
水道代の節約を考えると13mm口径で契約するのがベストです。しかし住んでいる家が20mm口径だと20mmで契約する必要があり、13mmで契約するには水道管を取り換える必要があります。
当然13mmに取り換えるのに費用が発生します。
水道の取り換え費用については工事の度合いにもよりますが下手をすると50万円くらいかかる可能性があります。工事費用と基本料金の差額を比較して
という場合は口径を変える選択肢もアリだと思います。
水道代の従量料金の計算方法
従量料金とは使用した水の量に応じて料金が変わる仕組みを指します。当然水道をたくさん使えば使うほど従量料金は増えていくので“ムダな水を使わない”事が水道代節約につながります。
ただし従量料金の計算方法はちょっと複雑です。例えば東京水道局の従量料金は以下のようになっています。
| 使用量 | 1㎥毎の単価 |
| 1~5㎥ | 0円 |
| 6~10㎥ | 22円/㎥ |
| 11~20㎥ | 128円/㎥ |
| 21~30㎥ | 163円/㎥ |
| 31~50㎥ | 202円/㎥ |
| 51~100㎥ | 213円/㎥ |
| 101~200㎥ | 298円/㎥ |
| 201~1000㎥ | 372円/㎥ |
| 1000㎥~ | 404円/㎥ |
出典:東京水道局
例えば1ヶ月に25㎥の水を使用した場合、従量料金は以下の計算によって導き出されます。
- 0円×5㎥=0円(1~5㎥利用分)
- 22円×5㎥×=110円(6~10㎥利用分)
- 128円×10㎥=1,280円(11~20㎥利用分)
- 163円×5㎥=815円(21~30㎥利用分)
0円+110円+1280円+815円=2,205円
つまり水を利用した水の量に合わせて段階的に1㎥当たりの金額が上がっていく仕組みになっています。25㎥使ったからと言って【163円/㎥】をかけて計算するわけではないので注意してください。
下水道料金の計算方法
水道代節約に関する多くは“上水”の計算方法はきちんと明記されています。しかし水道代には“下水道使用料も含まれます。
下水道料金とは水を下水に流した量に応じて発生する料金の事。例えばお風呂やトイレなどで水を大量に流せば流すほど下水道料金が増えていき、結果的に水道代も高くなるのです。
下水道料金は基本使用料560円と下水道に流した水の量にあわせて料金が異なる従量料金の合算になります。従量料金については以下の通りです。
| 使用量 | 1㎥当たりの料金 |
| 0㎥~8㎥ | 0円 |
| 9㎥~20㎥ | 110円/㎥ |
| 21㎥~30㎥ | 140円/㎥ |
| 31㎥~50㎥ | 170円/㎥ |
| 51㎥~100㎥ | 200円/㎥ |
| 101㎥~200㎥ | 230円/㎥ |
| 201㎥~500㎥ | 270円/㎥ |
| 501㎥~1,000㎥ | 310円/㎥ |
| 1,001㎥~ | 345円/㎥ |
出典:東京水道局
例えば1ヶ月に15㎥の下水を流した場合、下水道料金は以下となります。
560円+(110円×7㎥(15㎥-8㎥))=1,330円
水道料金は上水の利用料金と下水の利用料金の合算が請求されます。
地域によって水道代は異なる
先ほどお話ししたように、水道代の料金は
- 上水の基本料金
- 上水の従量料金(水を使った量)
- 下水の利用料金
の3つから構成されています。ただし具体的な金額は各地域によって異なります。
例えば上水道については
- 汲んできた水の綺麗さ
- 使用する人の人口
- 基本料金そのものも有無
によって水道代が変わってきます。特に“基本料金の有無”については自治体によっては基本料金を設定してしない全従量タイプの料金体系になっているところもあります。
また基本料金がゼロの代わりにメータ使用料という項目で一定金額の支払いが発生する自治体もあります。水道代の具体的な料金設定や金額等については住んでいるエリアを管轄している水道局のホームページ等を見て確認してください。
水道代が高い原因
総務省統計局が発表した平成28年度の水道代の世帯別平均金額(1ヶ月分)を調べると以下のようになっています。
| 世帯人数 | 水道代 |
| 2人 | 4,160円 |
| 3人 | 5,371円 |
| 4人 | 6,044円 |
| 5人 | 6,932円 |
| 6人以上 | 8,984円 |
参考:総務省統計局
世帯人数が多ければその分水を使う機会も量も増えるため水道代は増えてしまいますが、3人以上で住んでいる家庭であれば1ヶ月の水道代は5,000円以内に納められると家計的にはラクかもしれません。
ただ
・・・と言うように上記平均値を大きく上回る水道代を支払っている場合、水道代が高くなっている原因がどこかにあります。
各家庭によって原因はさまざまかと思いますが可能性として高いのは次の3点のいずれかではないでしょうか。
故障による水漏れ
例えば洗濯機に繋げてあるホースから水漏れしていたり、トイレのタンクが古くて水が完全に止まらなかったりなどといったちょっとした水漏れがあるだけでも水を使っていることには変わりないため水道代は高くなります。
東京水道局のホームページによると1ミリくらいの糸状の水が蛇口から1ヶ月間で続けているだけで水道料金は2,000円高くなると言われています。きちんと水が止まっているかは?は水道代に大きく関わるので
という事態になったらすぐに修理をお願いするようにしましょう。
また故障個所としては水道のメーターが壊れている可能性もあります。
水道メーターが壊れていると実際に使用した量よりも多い数字を表示するため“使っていない水道代”を支払う羽目になります。ただ水道メーターが故障しているかどうか?については自分では確認できないため
と感じたら念のために水道局に相談して確認してもらった方が良いと思います。
住んでいるマンションが親メーター式
マンションに住んでいる人に限定されますが住んでいるマンションが“親メーター式”を採用している場合どれだけ節水を頑張っても水道代は安くなりません。
親メーター式とはマンション1棟で水道局と契約し、同じマンションに住む世帯で水道代を分割して支払う方法を言います。つまりどれだけ自分の家で節水を心がけても別の世帯で水の無駄遣いをしていたら水道代は安くなるどころか高くなる可能性がある・・・ということ。
またマンションの世帯数が減ってしまえば分母が減ってしまうため1世帯当たりの支払う水道代は高くなってしまいます。親メーター式のマンションに住んでしまうと水道代節約に関しては努力ではどうすることもできません。
とマンションを探している場合は水道代が親メーター式でないか?は確認しておくように。
水の無駄遣いが多い
単純に水を使う量が多ければその分水道代は高くなります。例えば自宅で仕事をしていて水を大量に使う機会が多ければ水道代は自然と高くなりますよね?
水の無駄遣いが多い箇所や具体的な節約法についてはこれから紹介していきます。上記2つのどちらも該当しない場合は“無駄遣い”が水道代を高くしている原因なので1ヶ所ずつ水の使い道を改めて水道代を抑えていきましょう。
水道代節約の基本は『元栓』

水道代の節約で最初にやるべきことが水道の元栓を少し閉めておくことです。これだけで毎月の水道使用量が変わってきますし水道代も変わってきます。
家庭で使用する水道は地下に走っている上水道を通ってきます。その箇所には水道が使えるようにするための元栓と水道メーターがついています。
つまりこの元栓を通って自宅のあらゆるところで水が使えるようになります。ということはここの水の入り具合を狭めてしまえば必然的に使用する水を制限することができる・・・というわけ。
使う蛇口1つ1つを全開にしないよう気を使うのは慣れるまで大変だと思います。だったら自宅に入ってくる水の量を少なくしてしまえば自然と節水につながります。
たとえ蛇口を全開にして使っても元栓から水の流れが制限されますからね。水の無駄遣いを抑えるためにもまずは元栓を少し締めてから具体的な節水方法に取り組みましょう。
ちなみに水道の元栓は誰でも簡単に閉めたり開けたりすることができます。
新居に引越しした際に水を引き込む時にあらかじめ少し狭めておけば初月から水道料金の節約が実践できます。
ただしあまり締めすぎると今度は水の流れが悪くなり、生活に何かしらの支障をきたす可能性があります。
例えば水の出が悪くなって料理がしにくくなったり、トイレの水が流れなくなったり。いくら水道代を節約したいといっても生活に支障が出たら元も子もないので、普通に生活できるくらいの水の流れは確保しておきましょう。
ムダのない水の使い方で水道代を節約

水道の元栓を少し閉めてから各箇所の具体的な節約法を実践していきましょう。とはいっても、主に水道を使う場所というのは限られていますので、そこだけ注意すれば問題ありません。
自宅で主に水道を使う箇所とは
- トイレ
- お風呂
- 洗濯
- キッチン
の4ヶ所。つまり上記4か所の水の使い方を改めれば自然と水道代の節約につながります。
では各箇所でどのような水の使い方をすれば水道代の節約になるのか?をまとめました。全部を一度にやるのは忘れそう・・・という人は1つずつ習慣づけていってもらえばと思います。
トイレでの節水テクニック
自宅の中で最も水を使用する場所がトイレです。
トイレは水を流すだけで8~10リットルの水を使用します。金額すると約3円かかるためムダにトイレの水を流すだけでも3円の無駄遣いとなるわけです。
ただしトイレの水を流さないと衛生的に良くありませんから使ったら必ず流す必要はあります。トイレの節水で大事なのは
- 1回の水の流す量をなるべく最小限に
- 余計な水の流しはしない
の2つです。具体的には次の3点を意識するとトイレで使う水は節約できます。
トイレットペーパーを使いすぎない
トイレの水の量を減らすためにもトイレットペーパーの使いすぎは気をつけましょう。トイレットペーパーを大量に使用すると使用したトイレットペーパーを流すために水を多く使わないといけなくなりますからね。
またトイレットペーパーを使いすぎれば当然トイレットペーパーを買う頻度も多くなります。使わなすぎも問題ですが過度にトイレットペーパーを使うのもよくないので必要最低限の量を使うのを意識しましょう。
お尻の拭き過ぎはお尻に良くない?
水道代を節約するためにもトイレットペーパーの使いすぎはお勧めしませんが実は健康面でもお尻をきれいにしすぎるのは問題があると言われています。
お尻を強く拭き過ぎるとバリア機能が低下して皮膚を傷めてしまう危険性があります。便をした後綺麗にしたい一心で大量のトイレットペーパーで強く拭かなくてもきれいになるので適度な量を使うように。
水を流す時は大・小を使い分け
トイレの水を流すと「大」と「小」があります。ご存知の方も多いでしょうが大と小とでは流す水の量が異なります。
具体的に大なら約13リットル、小なら8~9リットルの水が流れます。つまりおしっこをしたのに「大」で流すと4~5リットルほどムダに流している・・・と言う計算になります。
最新式のトイレであれば節水機能が優れているため1度に流す水はもっと少なくできます。しかし大と小とで流す水の量が違う以上、水道代を節約するのであればきちんと使い分ける必要があります。
タンクにペットボトルを入れない
トイレの節水で昔から有名な方法として『タンクにペットボトルを入れる』があります。ペットボトルをタンクに入れればタンクに入る水の量が減るため水を使う量が抑えられる・・・というのが目的です。
しかしタンクにペットボトルを入れるとタンクの内部が破損したり故障の原因にもなります。
確かに2リットルのペットボトルをトイレのタンクに入れると約2リットルの節水ができる計算になります。しかし水の流れに応じてペットボトルが動き、それが原因でトイレが壊れて水が止まらなくなれば水道代だけでなくトイレの修理代まで増えてしまいます。
トイレが古くてなかなか節水ができないならいっそ最新のトイレにリフォームした方が良いでしょう。目先の節約ではなく長い目を見て節水を心がけてください。
お風呂での節水テクニック
トイレの次に水を使う箇所がお風呂です。お風呂に入るためには浴槽にお湯をはらないといけないため当然多くの水が使われます。
だからこそなるべく無駄な水を使わないようなお風呂の入り方が重要になってきます。またお風呂ではなくシャワーで済ませる人もいると思いますが
の目安についても言及します。具体的には次の3点を意識するとお風呂で使う水を節水出ると思います。
短時間で家族全員入る
基本的にお風呂は1人ずつ入ります。家族が多ければ当然最初の人が入ってから最後の人が入るまで時間がかかってしまいますよね?
お風呂は時間が経てばどんどんお湯の温度が冷めていってしまいます。お湯が冷めれば追い炊きするなどして新しいお湯を入れるため当然追加の水(お湯)が必要になります。
追い炊きをしないためにもお風呂を沸かしたら短時間で家族全員が入るよう心がけましょう。追い炊きをしなければその分水道代だけでなくガス代も節約できます。
3人家族以上ならシャワー入浴はNG
東京水道局によるとシャワーを1分間流しっぱなしにすると約12リットルの水を使うと言われています。つまり10分間シャワーを浴びると120リットルの水を使用する計算になります。
一方で家庭用のお風呂に入る時、約200リットルのお湯が必要となります。また追い炊きやシャンプーの泡などを洗い流す水は1人当たり30リットルと言われています。
つまりシャワー2人分の水の量(240リットル)と2人がお風呂に入る水の量(200リットル+60リットル)はほぼ同じくらいと考えられますよね?
以上の点から3人以上の家庭の場合全員がシャワーを浴びるよりもお風呂を沸かした方が水を使う量は少なく済む・・・と言えます。一人暮らしの人はシャワーの方がいいかもしれませんが家族と住んでいると
シャワーの方が水道代は安くなる
・・・と言うのはウソになるのでお間違いのないように。
浴槽のお湯は2日に1回交換
先述したように水を使う量だけを考えると1人でお風呂に入るならシャワーの方が水道代の節約になります。しかし一人暮らしの人で
といってお風呂に入る人もいると思います。そんな人は毎日お風呂を沸かすのではなく2日に1回お湯をはり替える・・・という習慣をつけてみましょう。
そもそも1人がお風呂にはいっただけお湯はそこまで汚れません。ならば翌日も同じお湯を使えば追い炊き分だけで済むため水道代は節約できますよね?
また家族が3人以上いる家族もお風呂のお湯を全てはりかえるのではなく半分だけ替えるという手段もあります。そうすれば日々お風呂に使う水の量は半分になるため水道代も抑えられます。
洗濯の節水テクニック
トイレやお風呂と同様に多くの水を使うのが洗濯です。
最近は洗濯機の性能が上がり節水効果が高い物が増えてきました。そのため古い洗濯機を使っているのであればいっそ新しい洗濯機に替えるだけでも節水効果は期待できます。
さらに次のような事を意識するとより洗濯に使う水を抑えられます。
お風呂の残り湯を利用する
洗濯に使う水を抑える最も効果的な方法の1つがお風呂の残り湯での洗濯です。
お風呂の水を無駄にしないための最も有名な方法の1つが、お風呂で使ったお湯を洗濯に使うというものです。これによって洗濯に使用する水を約半分節約することはできます。
もしお風呂の残り湯で洗濯するのに抵抗があるのなら「すすぎ」だけ水道水を使うようにしてください。すべてをお風呂のお湯で洗濯するよりも水道代は高くなりますが、それでもすべてを水道水で行うよりは節水効果は高いです。
洗濯する回数を減らす
洗濯は別に毎日する必要はありません。ある程度洗濯物が溜まった時にまとめて選択した方が水道代の面では大きな節約になります。
洗濯機には容量があります。選択すべきものが容量の1/3もないのに洗濯機を回すのはちょっともったいないですよね?
1人暮らしや夫婦2人暮らしであれば2日に1回くらいの洗濯でも十分生活できます。ある程度洗濯物を貯めてから一気に洗って水道代や電気代を節約しましょう。
ただしだからと言って洗濯物の“貯めすぎ”は良くありません。
洗濯ものを入れすぎるとかえって電気代が高くなったり汚れが落ちにくくなって二度洗いが必要になったりします。洗濯機の定格容量の2/3くらいまで貯まったら洗濯機を回すようにするのがいいでしょう。
洗うものに応じてすすぎの回数を減らす
少し上級者向けの節約方法ではありますが、洗うものに応じてすすぎの回数を減らすのも水道代の節約につながります。
例えば汚れがひどくないものや簡単に汚れが落ちそうなものばかりを洗う時、洗濯機の設定を変えてすすぎを1回減らします。そうすればすすぎ1回分の水を使わなくてもいいため水道代は抑えられますよね?
もちろん汚れがひどかったりすればしっかり洗わないといけないのですすぎの回数を減らすのは良くありません。洗濯物を見て
と思った時にすすぎの回数を減らしてみてください。
洗剤を入れすぎない
汚れをしっかり落とすために必要以上に洗剤を入れてしまう人もいるかもしれませんが“水道代”の観点から見るとあまりよくありません。
なぜなら洗剤を入れすぎると余計にすすぎがひつようになるからです。すすぎをするために新しい水を洗濯機の中に入れる必要がありますが洗剤が多いとすすぎの回数が増えてしまう可能性があるからです。
各洗剤はパッケージ等できちんと適量を表示しています。洗剤を入れすぎても汚れが落ちやすくなるわけではないので適量以上の洗剤を入れるのはやめましょう。
キッチンでの節水テクニック
キッチンでの節水でまず大事なのは“水の出しっぱなしをしないこと”です。
キッチンの水を5分間出しっぱなしにするだけで約60リットルの水が使われます。これを1ヶ月行うと約2,200円の水道料金がかかります。
それ以外にもキッチンでの節水方法はいろいろあります。トイレやお風呂に比べると使用用途の幅が広いため節約のためのテクニックも多岐にわたります。
食洗器を使って洗う
一人暮らしだとあまり意味はありませんが3人以上の家族の場合、食器を手で洗うよりも食洗器を使った方が水道代は節約できます。
食洗器は比較的大きいため場所を取る・・・というデメリットはあるものの、洗う食器が多ければ多いほど使う水の量は手洗いよりも少なくなるため思い切って食洗器を購入するのも水道代節約の点ではアリです。
ただし和食器や高級食器などを食洗器で洗うと食器(もしくは食洗器)が壊れる恐れがあるので注意してください。
米のとぎ水を掃除に使う
お米を洗う際にでる“米とぎ汁を捨てず再利用するのも水道代を節約する方法の1つです。他の節約法と違って水道代そのものを下げる効果はありませんが間接的に節約に貢献してくれます。
例えば米とぎ汁を植物などに与えればわざわざ新しい水を使わなくて済みます。しかも米とぎ汁にはビタミンやミネラルが含まれているため植物がより丈夫に育つと言われています。
また汚れた食器を米とぎ汁につけておくと汚れが落ちやすくなります。洗剤を使う量も減るためすすぎに使う水の量も抑えられますから間接的な節水につながります。
食器の汚れを先に落としておく
例えば食器や鍋・フライパンなどについている汚れをいきなり水洗いするのではなく使用済みのクッキングペーパーや新聞紙で拭くだけでも節水の効果はあります。
しつこい汚れを先に落としてしまえば必要以上に水も洗剤も使わずに汚れが落とせます。わざわざ新しいクッキングペーパーを使うと紙がもったいないので“捨てる予定のもの”を再利用して汚れを落としてから食器を洗うようにしてください。
また調理する際に野菜などを洗った水を洗い桶に貯めておき、食べ終わった食器を桶に入れて水につけるだけでも汚れは落ちやすくなります。一手間かかりますが一手間かけることで使う水を減らせるのでぜひ習慣にしてください。
水道代節約グッズを活用する

先ほど
- トイレ
- お風呂
- 洗濯
- キッチン
の各節水方法について紹介しました。上記の方法は普段の水の使い方を工夫することで水を使う量を抑えられるため水道代の節約につながります。
とはいえ、水の使い方の工夫しようとしても普段の使い方を改善するため最初は戸惑ったり忘れてしまったりします。当然節約につながる使い方をしないと水道代は節約できません。
という人はまずは水道代節約グッズから使ってみてはどうでしょう。
日用品の中には水道代節約につながるグッズがあります。水道代を節約するために多く人が利用している節約グッズを8つ紹介するのでぜひ使ってみてください。
トイレで使える節約グッズ
トイレで使える節約グッズとしてお勧めなのが次の3つです。ただしトイレのメーカーやタイプによっては利用できない節約グッズもあるので節約グッズを買う際は
をしっかり確認してから使う節約グッズを選びましょう。
ウォーターセーバー
トイレで流す水を40%節水できる節約グッズ。使い方はトイレタンクのフロートの上に取り付けるだけで特に工具も必要ないため誰でも簡単に取り付けられます。
ウォーターセーバーを取り付けるとトイレのレバーが重くなります。普段と同じ感覚でトイレのレバーをひねっても水が出にくいのでウォーターセーバーを取り付けてからはトイレのレバーを気持ち長めに回すよう心がけてください。
価格は1,000円前後なのでお手軽なのもお勧めする理由の1つ。長く同じトイレを使っている家庭にはおすすめです。
水洗トイレ節水器ロスカット
ウォーターセーバーと同様にトイレの水を流す量を抑えてくれる節約グッズ。トイレが水を流したり止めたりするフタの閉まるタイミングを早めてくれるため余計な水の流れを防いでくれる働きがあります。
ただしボタンで水を流すタイプのトイレやタンクの位置が高いところにある古いタイプのトイレには水洗トイレ節水器ロスカットは利用できません。また節水型のトイレにも使用できないので事前に自分の家のトイレのタイプを確認してから利用しましょう。
価格は2,500円と若干高めに感じるかもしれませんが、節水に対する費用対効果を考えるとお手頃な価格と言えるでしょう。
(2024/07/27 08:07:56時点 楽天市場調べ-詳細)
ドルフィンセーブ
TOTOのトイレでのみ利用できる節約グッズで、4人家族であれば年間8,000円以上水道代を節約できるグッズです。使い方はバルブに取り付けるだけ。
ドルフィンセーブをバルブに取り付けると空気穴からの浮力がなくなり水を流すフタが早く閉じるようになります。また節水量を9段階に調整できるため各家庭の水の勢いに合わせた使い方ができます。
価格は5,000円前後と少し高めですが1年使い続ければ元が取れるので自宅のトイレがTOTO製の家庭にはおすすめです。
お風呂で使える節約グッズ
お風呂で使える節約グッズでおすすめなのが次の3つです。具体的に水の勢いを意図的に抑えるものや追い炊きの回数を減らしてくれるタイプの節約グッズが多いです。
シャワーヘッド
節水効果があるシャワーヘッドは通常のシャワーヘッドと違い穴の数が少なくなっていり穴の大きさが小さかったりします。そのため水が出る量が抑えられるため水道代が抑えられます。
特におすすめなのがシャワーヘッドamane天音。穴の大きさが0.19㎜でミストを浴びている感じがします。節水効果も低水圧だあれば4人家族の場合最大24%、高水圧だと最大35%の節水が期待できます。
(2024/07/27 08:07:56時点 楽天市場調べ-詳細)
お風呂保温シート
浴槽にはったお湯の温度を下げにくくする節約グッズ。お湯が冷めにくかったら追い炊きの必要性がないため水道代の節約につながります。
使い方はお湯をはった浴槽に保温シートをかぶせるだけ。価格も500円前後で購入できるため気軽に利用できるのもメリットです。
(2024/07/27 08:07:56時点 楽天市場調べ-詳細)
キッチンで使える節約グッズ
キッチン用の節約グッズは蛇口に取り付けるタイプから食器洗いに役立つグッズまでさまざまあります。中でも次の3つは誰でも使いやすいのでお勧めです。
クリシャワー
蛇口に取り付けるだけで最大60%の節水効果が期待できる節約グッズです。水量は好みで調整できるため使い方にあわせて調整すればストレスも感じないはず。
価格も2,700円前後なので決して高くはありません。蛇口先端にねじ山がなかったり内側ネジタイプの蛇口には利用できないため利用する際は事前に蛇口のタイプを確認しておきましょう。
(2024/07/27 08:07:56時点 楽天市場調べ-詳細)
米とぎシェーカー
お米と水をいれてシャカシャカ振るだけで米とぎができる節約グッズ。少ない水で米とぎができるため節水効果が高いのが特徴です。
時間は普通に米とぎをするのと変わりませんが、水を出しっぱなしにする必要がないうえに水に手をふれずに米とぎができるため冬の寒い時期には重宝します。価格も1,300円前後と手ごろなので“お手軽料理グッズ”として使ってみてはいかがでしょう。
たためるシリコン洗い桶
あらかじめ食器を水につけてから洗うの効果的です。この時洗い桶があると便利ですが家のキッチンの広さによっては邪魔になるデメリットがあります。
しかしこの洗い桶は使わない時は畳めるため一人暮らしの人でも利用できます。またシリコン製のため傷つきにくく汚れもつきにくいため衛生面も心配ありません。
価格は2,000円前後と洗い桶として少し高めですが長く使えるのを考えると決して高くはないかと。洗い桶はキッチンでの節水方法においてはま明日となアイテムなので自宅のキッチンに合った洗い桶が見つからない人はこの洗い桶を活用してもいいのではないでしょうか。
節水を心がけると水道代はいくら節約できる?

これまで水道代を節約するための方法として
- 水道料金の計算方法の把握
- 水道の元栓を少し締める
- 各箇所の具体的な節約法
- 節約グッズの活用
を紹介してきました。実際に上記のような対策をすれば少なくとも水の無駄遣いが減るため水道代も抑えられると思います。
では実際に節水方法を実践すればどのくらい水道代が節約できるのか?
インターネット上にある節約ブログを調べてみたところ、色々な節水方法を実践して水道代を節約した例がたくさんありました。例えば
お風呂のお湯を洗濯に使ったら2ヶ月で1,800円水道代が節約できた
シャワーヘッドを変えただけで年間7,600円節約できた
元栓を締める、
シャワーを使わない、
ご飯を作る時に使ったお湯を食器洗いに活用、
洗濯は2日に1回まとめ洗い。これを徹底したら2ヶ月の水道代が7,000円を切りました
トイレの流し方やお風呂の入り方を改善して1ヶ月に約3,000円の水道代節約に成功した
などなど。
節約ブログで紹介されていた具体的な節水方法は当ページでも紹介したものばかりでした。ただ1つの節水方法を突き詰めている人や色々な節水方法を同時に取り組んでいる人など取り組み方は様々な印象でした。
理想は“節水に関するすべての方法を実践する”だと思います。しかしいきなり全部をやろうとすると混乱してしまうのでできるところから取り組んでみてください。
一人暮らしの水道代節約は効果が薄い?
これまで水道代の具体的な節約方法について紹介してきました。当然家庭によって節水による節約効果は変わってきます。
中でも一人暮らしの水道代節約は思った以上に効果が実感できないかもしれません。
東京水道局によると一人暮らしの人が1ヶ月に使う水の量は平均8.2㎥と言われています。つまり一人暮らしの月間の水道代は
基本料金:860円
従量料金:(8.2-5)×22円=70.4円
下水料金:560円+(9-8.2)×110円
合計:1,578円
(※実際の水道代請求は2か月に1回まとめてくるため支払う額は2,980円)
となります。
上記の金額から水道代を節約しようとしても、できるのは月間の水の使用量を5㎥未満するくらい。節約効果は月間で100円ほどしかありません。
仮に水を一滴も使わなくても基本料金(860円)と下水道料金(560円)は絶対にかかってきます。2つの料金を足しても1,420円ですから一人暮らしの人が節水を心がけても大きな節約効果は期待できないのです。
一人暮らしの人で注意すべきは“水の無駄遣いを減らす事”のみ。
一人暮らしの人は現在水道代の支払いが1ヶ月あたり1,500円前後であれば無理に節水に力を入れる必要はないと思います。
まとめ
いかがでしたか?
水道代を節約する方法は決して難しくありません。水道代の仕組みを理解し、水の使い方を改めれば割と簡単に節水ができると思います。
水道代の節約方法は習慣化できれば毎月一定の節約効果が生まれます。当ページを参考に水の使い方を改善して上手に水道代を節約してください。