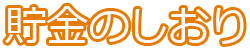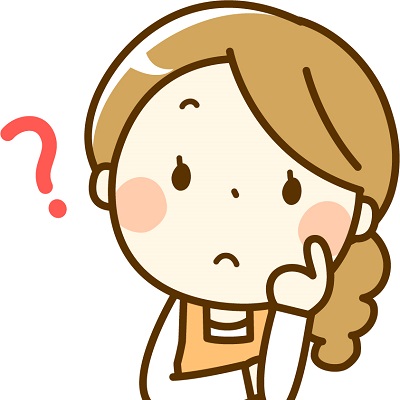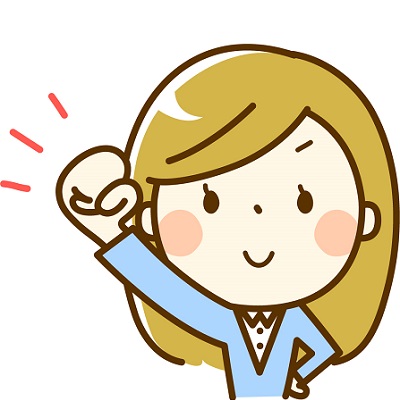一般的に電気代は夏と冬に高くなると言われています。特に冬の電気代は1年の中で最も高くなります。
季節によって過ごし方が異なるため電気の使い方や使う家電も変わってきます。では冬の電気代が高くなる原因とはそもそもどこにあるのか?
当ページでは
- 冬の電気代にいくらかかっているのか?
- なぜ冬の電気代が高いのか?
- 冬の電気代を抑える具体的な節約術
を中心にお話ししていきます。その場だけでなく年間の電気代を抑えるためにも冬の電気の使い方はとても重要なのでぜひ参考にしてください。
目次
冬の電気代は平均いくら?

冒頭でも言いましたが冬は1年を通して電気代が高くなりがちな時期でもあります。その証拠に総務省統計局が発表した月別の電気代(2018年)を見ると寒い時期に電気代が高くなっているのが分かります。
| 月 | 電気代 |
|---|---|
| 1月 | ¥13,404 |
| 2月 | ¥14,222 |
| 3月 | ¥13,534 |
| 4月 | ¥11,192 |
| 5月 | ¥9,439 |
| 6月 | ¥8,286 |
| 7月 | ¥8,666 |
| 8月 | ¥10,790 |
| 9月 | ¥11,354 |
| 10月 | ¥9,799 |
| 11月 | ¥8,772 |
| 12月 | ¥9,719 |
引用:総務省統計局
上の表を見てもらえば分かる通り、1月~4月まで電気代の平均が1万円を超えています。8月、9月も1万円を超えていますが冬場の電気代はさらに3,000~4,000円高いのが分かりますよね?
このように冬は電気代が最も高くなる季節でもあります。いくら春や秋に節電を頑張っても冬の時期に節電をしないと年間の電気代は大きく節約はできないでしょう。
世帯別に見ても冬の電気代は高いのか?
上記の表を見る限り1年のうちで冬は最も電気代がかかる時期だ・・・というのが分かったかと思います。では“世帯別”にみても電気代は夏よりも冬の方が高いのでしょうか?
総務省統計局の家計調査では各世帯の支出も発表されています。そこで各世帯(単体世帯~4人世帯)の電気代の平均を冬の時期(2018年1月~3月)と夏の時期(2018年7月~9月)の各3ヶ月の平均を比較してみました。
| 世帯人数 | 冬の電気代 | 夏の電気代 | 差額 |
| 1人 | 2,366円 | 1,863円 | 503円 |
| 2人 | 12,085円 | 9,331円 | 2,754円 |
| 3人 | 14,291円 | 10,039円 | 4,252円 |
| 4人 | 14,835円 | 11,039円 | 3,796円 |
世帯によって冬と夏の差額に違いがありますがどの世帯も冬の電気代よりも夏の電気代に比べて高くなっているのが分かります。
つまり世帯に問わず冬の電気代を抑えることが年間の電気代の節約につながると言えるでしょう。
冬になると電気代が高くなる原因

先ほど紹介したようにどの世帯でも冬になると電気代は高くなります。
と感じる人も多いでしょう。冬の電気代が他の季節に比べて高くなる傾向にあるのは次の3つが原因と考えられています。
室内と室外の温度差が激しい
先ほど紹介した月別の電気代の平均を見てみると冬だけでなく夏もまた電気代が高くなっているのが分かります。夏も冬も室内の快適温度と実際の温度が大きく違う季節でもあります。
気温と快適温度が異なるとエアコンを使います。エアコンは家電の中で最も消費電力が多いためエアコンの利用機会が多くなる夏と冬は電気代が高くなりがちになるのです。
と思うでしょう。
その原因は“温度差”が関係してきます。
例えばエアコンの冷房を28℃、暖房を20℃で使用すると仮定して2018年の東京の夏の気温と冬の温度との温度差を比較したところ以下の表のようになります。
最高気温で比較
| 夏 | 冬 | |
| 気温 | 32.7℃(7月) | 9.4℃(1月) |
| 設定温度 | 28℃(冷房) | 20℃(暖房) |
| 温度差 | 4.7℃ | 11.6℃ |
最低気温で比較
| 夏 | 冬 | |
| 気温 | 25.0℃(7月) | 0.6℃(1月) |
| 設定温度 | 28℃(冷房) | 20℃(暖房) |
| 温度差 | -3℃ | 19.4℃ |
※各季節の最高気温は、夏は最も高い月、冬は最も低い月を選出しています。
※参考:気象庁
上記の表を見ればわかる通り、室内の快適温度と外の気温の温度差は夏よりも冬の方が大きいのが分かります。つまりエアコンをはじめとする空調機器の稼働時間は夏よりも冬の方が長くなりやすいのです。
家電の稼働時間が長ければ当然消費する電力も多くなります。冬の電気代が高いのは空調機器の稼働時間がどの季節よりも長いのが大きな原因と1つと言えるでしょう。
洗濯をする回数が増える
冬の電気代が高くなる理由として『洗濯をする量が増えるから』とも言われています。
夏の場合気温が暑いので着る服は基本薄着になるため、洗濯をする服の量はあまり多くありません。仮に汗をかいて着替えてもたかが知れていると思います。
対して冬は寒いため何枚も重ね着をします。つまり1日あたり2~3枚くらいの服が必要となるため必然的に選択をする服の量が増えるのです。
さらに冬場は日照時間が短いうえに冬に着る服は生地が分厚くなっています。そのため雨や雪が降ると乾きにくくなり乾燥機を使う機会も増えます。
乾燥器は洗濯機に搭載されている乾燥機能を使う人もいれば浴室乾燥機を利用する人もいます。どの乾燥機を使うか?によって電気代は変わってきますが冬の方が乾燥機を使う機会が増えやすいため電気代が高くなりやすいです。
乾燥器を使うと電気代はどのくらいかかる?
冬になると乾燥機を使う機会が増えやすい・・・と言いましたが乾燥機を使うとどのくらい電気代がかかるのか?一言で乾燥機と言っても色々なタイプの乾燥機があります。
例えばパナソニックから販売されている乾燥機は
- 電気乾燥機
- 洗濯乾燥機(ドラム式)
- 洗濯乾燥機(タテ型式)
- 浴室乾燥機
の3タイプ4種類があります。各乾燥機の消費電力と電気代は以下の通りです。
| 消費電力 | 1回(2時間使用)の電気代 | |
| 電気乾燥機 | 800W~1,495W | 49円~81円 |
| 洗濯乾燥機(ドラム式) | 890W | 約48円 |
| 洗濯乾燥機(タテ型式) | 1,100W | 約59円 |
| 浴室乾燥機 | 1,250W | 約67.5円 |
※電気乾燥機は強モードと弱モードの2つの稼働方法があり、それぞれの稼働方法で消費電力が異なります。また室温の設定によっても消費電力が変わります。
※上記電気代は主要電力会社10社の平均単価『27円/kWh』で計算しています。
引用:ダイナビSwitch『乾燥機の電気代は高い? 4つの家電で計算してみた!』
このように
- 冬になると着る服が多くなるため洗濯物が増えやすい
- 冬の衣類は厚手のため乾きにくく乾燥機を使う機会が増えやすい
という2つの理由から洗濯に関する消費電力が多くなり、それが電気代が高くなる原因につながる・・・と言われています。
日照時間が短い
冬の電気代が高くなる原因として挙げられるのが“照明の電気代が高くなるから”です。
冬の時期は1年の中で最も日照時間が短くなります。日照時間が短い・・・ということは外が暗い時間が長いため照明をつけている時間も自然と長くなるのを意味します。
例えば気象庁の2018年のデータから東京の夏の日照時間(6~8月)と冬の日照時間(12~2月)を比較してみました。
つまり単純計算で冬は夏よりも照明を使う時間が89時間長いと言えます。8~10畳用の家庭用蛍光灯式シーリングライトの消費電力が75Wと仮定すると6,675W多く電力を消費するため電気代もその分増えるのは当然ですよね?
冬の電気代を節約する具体的な方法

これまで冬の電気代が高い主な原因として
- 快適温度と外の気温の温度差
- 洗濯をする量が増える
- 照明を使う時間が長い
の3つを紹介してきました。どの原因も冬だからこそ起こるものですからある程度は仕方がないところもあるでしょう。
しかしだからといって“無策”のまま冬を過ごすと電気代はかさむ一方です。そうならないよう“冬の節電対策”をしっかり考え、電気代を抑える行動を取っていきましょう。
冬の電気代を節約する具体的な方法は以下の5点です。理想は全てできれば・・・ですが、生活習慣などのクセなどもあるのでまずは
というものから取り掛かって冬の自宅での過ごし方や家電の使い方を変えていってみましょう。
エアコンの使い方を改善
冬の時期に最も電力を消費するのはエアコンです。夏ほど大きな割合を占めないものの自宅で使う電力の約3割がエアコンと言われています。
エアコンの節電方法については
- 暖房の温度は20℃で固定
- 運転は自動運転
- サーキュレーターを使って風を動かす
などといった行動があります。エアコンの消費電力を抑える具体策については下記ページで詳しく紹介していますのでぜひ参考にしてください。
暖房器具の使い方を改める
といってエアコン以外の暖房器具を使って室内を温めている家庭も少なくないでしょう。室内を温める方法はエアコン以外にも様々な家電がありますからね。
当然、各暖房器具によって“使い方”も変われば消費電力も異なります。各暖房器具の特徴や効率よく節電する使い方は以下の通りです。
ファンヒーター
ハロゲンヒーターなどのファンヒーターは熱を局部的に放出するため、狭い部屋を暖めるのに向いています。またスイッチをつけてから熱が放出されるまでの時間が短いためエアコンと同時に使うと部屋の温度が早く上がり、エアコンの稼働時間が短くなります。
電気代はメーカーや稼働モード(強・中・弱)によっても異なりますがおよそ12円~27円ほどと言われています。具体的な電気代は以下の通りです。
| ヒーターの種類 | 電気代 |
| セラミックファンヒーター (木造6畳/コンクリート8畳) |
強:32.4円 弱:14.9円 |
| ハロゲンヒーター (3畳) |
強:27円 中:18円 弱:8.9円 |
| カーボンヒーター | 強:24.3円 弱:12.1円 |
| オイルヒーター (8畳タイプ) |
12.7円 |
| 石油ファンヒーター (木造10畳/コンクリート13畳タイプ) |
約21.6円 |
※1kWhあたり27円として計算しています。
※電気代は1時間当たりの料金です。
※石油ファンヒーターを稼働させるには灯油が必要になりますが灯油購入費は考慮していません。
ファンヒーターを使う場合は使う部屋の広さにあわせたものを購入しましょう。
例えば3畳タイプのハロゲンヒーターだけでひろいリビングを温めようとすると稼働時間が長くなってしまい電気代が高くなってしまいます。
といって小さいファンヒーターを買うのではなく使う部屋の広さに合ったファンヒーターを使うのが冬の電気代の節約につながります。
またタイマー機能がついていないタイプのファンヒーターの場合は待機電力を出さないようすると完璧です。使わない時はコンセントから抜くから節電タップにつないでスイッチを切るなどの工夫をすると余計な電力消費が抑えられますからね。
ホットカーペット
ホットカーペットは中に電線が通っているカーペットで電気を通すと電線が熱も持ち、その熱によって温める暖房器具です。温まる時間も早くカーペットの上にいれば常に下から暖かい熱が伝わってきます。
ただし一歩カーペットから離れるとホットカーペットの効果は全く得られません。エアコンをつけるまでもないけど
と感じたり、特定の場所に居続ける時はホットカーペットだけ使い、それ以外の暖房器具は使わないようにすると電気代を抑えつつ自宅で快適な時間が送れるでしょう。
ホットカーペットの電気代は2畳タイプのもので強状態なら9.0円、中状態なら6.2円です。(1Kwhあたり27円で計算)メーカーによっては強だと熱く感じるので中状態で使うのが良いと思います。
こたつ
昔からある暖房器具の1つがこたつです。テーブルの下にある発熱体を設置し、布団でテーブル全体を覆うことで覆われた部分から暖かい熱が閉じ込められ、その部分に足を入れて温まる暖房器具です。
ホットカーペットと同様に特定の場所を温める暖房器具のため、一歩でもこたつから足を出したら暖房効果はゼロになります。ただしこたつに入ると体感温度が上がるためこたつ以外の暖房器具(ファンヒーターやエアコンなど)の設定温度を下げられるメリットがあります。
1時間あたりの電気代は強なら4.3円弱なら2.2円です。(1kWhあたり27円で計算)
基本的にこたつと他の暖房器具と併用して使うのですがこたつを使う時は設定温度を少し下げたり暖房器具の強さを『弱』で使うなど全体的に消費電力がかからないように使うのがポイントです。
室内の暖かい空気を逃がさない
室内を暖房で温める際に気を付けるポイントとして“窓”があります。
熱は暖かい方から冷たい方に流れていきます。そのため暖房器具によって温めた熱も窓を通して外に逃げていってしまうのです。
熱が逃げてしまえば暖房器具の稼働時間も長くなってしまいます。それを防ぐために室内の温められた空気を逃がさない工夫も大切です。
例えば窓に断熱シートを貼って熱が外に逃げないようにしたりする・・・とか。
断熱シートには主に
- 紫外線をカットするオールシーズン用
- 結露防止や暖房効果がある冬用
の2種類があります。冬の電気代を節約するなら後者の断熱シートを購入して窓に貼ると暖房器具の稼働時間が減って電気代の節約につながります。
断熱シートによる節電効果と選び方については下記ページで詳しく解説しています。
照明の消費電力削減を意識する
冬の電気代が高くなる原因の1つして『照明をつける時間が長い』を挙げました。冬は夏に比べて日照時間が長いためどうしても照明の使用時間が長くなりますからね。
もちろん部屋が暗くなれば照明はつけるべきだと思います。しかし照明をつける機会が多い分“消し忘れ”も多くなるため照明による電気の無駄遣いはしないよう注意してください。
具体的には
- 誰もいない部屋の照明は消す
- 自宅を外出する前に照明の消し忘れをチェック
などなど。
また照明をLEDに替えると照明の電気代が節約できます。12畳向けの照明で蛍光灯とLEDの消費電力を比較したところ
蛍光灯:120W
LED:50W
と蛍光灯の半分以下の電力となります。
ただしLEDのデメリットとしては
- 購入価格が蛍光灯よりも高い
- LED用の照明器具(シーリングライト)を買う必要がある
と初期費用がかかってしまう点。いきなり自宅にあるすべての照明をLEDに替える必要はないので、リビングなどよく照明をつける部屋から優先的に買い替えるだけでも十分に節約になるでしょう。
自宅で過ごす時の服は厚めに
もっとも多くの電気を消費するのはエアコンや暖房器具などの“空調”に関する家電です。そのため暖房器具の稼働を少しでも抑えられれば節電につながります。
と考えた時、もっとも簡単な方法は自宅で過ごす服装の改善です。具体的には暖かく防寒対策に強い服を“部屋着”として着ていれば暖房器具の強さを弱めても自宅で快適に過ごせます。
冬の部屋着にする服を選ぶポイントとしては
- やわらかい手触りの生地のもの
- 軽くて暖かいもの
の2点を重視するといいでしょう。例えばフリースやコットンでできた服がおすすめです。
また下着もユニクロが販売している『ヒートテック』のような発熱効果がある生地の下着を着ると暖房に依存せず過ごせます。価格も1枚1,000円前後から購入できるので割と手軽にできる防寒対策だと思います。
電気料金見直しは“電気代節約”の基本

冬の電気代に限らず年間通して電気代を抑える方法として近年多くの人が取り組んでいるのが“電気料金の見直し”です。
以前は契約できる電力会社が限られていたため、電気料金やプランを特に気にせず契約していました。しかし平成28年より電気の小売業参入が自由化したのをきっかけに各企業が色々な電力料金のプランを打ち出すようになりました。
電気料金を見直すことで1W当たりの電気代が安くなります。つまり今までと全く同じ使い方をしても電気代の節約になる・・・ということ。
さらにここで紹介した冬の電気代の節約術や各家電の使い方を改善して節電を心がけるとさらに電気代は今まで以上に安く抑えられます。
と考えている人はぜひ電気料金の見直しから始めてみるといいかもしれません。電気料金の見直しについては下記ページで詳しく解説していきます。
まとめ
いかがでしたか?冬は知らず知らずのうちに電気代が高くなりやすい時期でもあるので、そのことをしっかり自覚して上手に家電を使って節電をしてください。
冬の電気代が節約できれば1年を通した電気代も抑えられるはず。自宅も懐も温かくなるよう冬の自宅での過ごし方や家電の使い方を振り返ってみてはいかがでしょう。