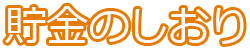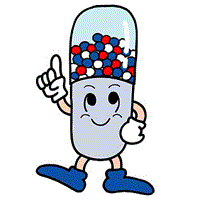サラリーマンが節税対策を行う上で絶対に知っておくべき事の1つが「確定申告」です。確定申告についての基本的な知識と有効活用法さえ知っていればサラリーマンでも簡単に節税できると思います。
しかし多くのサラリーマンが確定申告をした経験もないし基礎的な知識もないでしょう。なぜならほとんどのサラリーマンは確定申告をしなくても税制上問題ないからです。
確かにサラリーマンは毎年確定申告をしなくても大丈夫です。しかし特定の条件に該当する人は確定申告が必要だったりした方がお得になるケースが多分にあります。
そこでここでは、サラリーマンが行う節税対策の基本ともいえる“確定申告”についてお話ししていこうと思います。
確定申告とは?

まず「確定申告が何か?」というところからお話しします。
確定申告とは前年の収入を国に申告すること。この申告した額によって納税額が決定します。Wikipediaでは確定申告を次のように定義しています。
個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること
引用:Wikipedia
申告する期間は毎年2月中旬から3月中旬にかけて行われます。以前は税務署など所定の場所に申告用紙を書いて提出しないといけませんが近年はインターネット(e-tax)を使って自宅から申告できるようになっています。
ちなみに確定申告をしないといけないのに忘れてしなかった場合、無申告加算税や延滞税など納税額が増えてしまいます。確定申告が必須な年は忘れずに行いましょう
さらに確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらも確定申告には違いありませんが両者には大きな違いがあります。
青色申告とは?
青色申告とは日々の取引や収支を帳簿に記帳して申告する方法を言います。青色申告をするためには税務署に事前に『青色申告承認申請書』の提出が必要となります。(青色申告承認申請書は税務署に行けばもらえますのでその場で必要項目を書いて印鑑を押せばいいだけです。)
青色申告の特徴としては次の3点です。
控除が最大65万円受けられる
青色申告の最大のメリットは受けられる控除が大きい点です。青色申告をすると『特別控除』として最大65万円の控除が受けられます。
ただし青色申告をすれば確実に65万円の控除が受けられるわけではありません。65万円の控除を受けるには次の条件をクリアする必要があります。
事業所得か不動産所得がある
青色申告の対象となるのは
- 事業所得(商売で得た所得)
- 不動産所得(不動産の売買や賃貸で得た所得)
- 山林所得(山林を伐採もしくは立ち木のまま譲渡して得た所得)
の3種類です。この3つの所得のいずれかが発生していないと青色申告はできないのですが実は山林所得だけでも青色申告で65万円の特別控除が受けられません。
つまり事業所得か不動産所得が発生している人のみ特別控除が受けられるのです。
さらに不動産所得にも条件があり“事業”として不動産所得を受け取っているのを認めてもらう必要があります。要するに
というのが認められないと青色申告をしても65万円の特別控除は受けられません。
複式帳簿で記帳している
帳簿のつけ方には“単式帳簿”と“複式帳簿”があるのですが、青色申告で65万円の控除を受けるためには“複式帳簿”で記帳する必要があります。
複式帳簿とは売り上げや経費などを複数の帳簿に記入する方法を指します。2つの主要簿(仕訳帳と総勘定元帳)と6つの補助簿(現金出納帳、預金出納帳売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳)に分けて必要な帳簿に必要項目を書いていきます。
・・・と悩む人がいるかと思いますが、今の会計ソフトは必要な数字を入力すれば自動的に複式帳簿で記帳されるようになっています。簿記の知識がない人は会計ソフトを買って入力するのが最も安全だと思います。
申告期限を守る
確定申告は毎年2月中旬(だいたい15日前後)から3月中旬(だいたい15日前後)が申告期間となっています。この期間内に申告をしないと65万円の控除は受けられません。
ちなみに青色申告の特別控除は65万円のほかに10万円の控除もあります。申告が遅れた場合65万円の特別控除は受けられませんが10万円の控除は受けられます。(ただし遅延して事によって延滞税等が発生するためプラスマイナスで考えたらマイナスになる可能性が高いです)
2020年分より65万円受ける条件が変わる
今までは上記3つの条件をクリアすれば特別控除が65万円になりましたが、2020年分の確定申告から65万円の特別控除を受ける条件が追加されます。具体的には以下の2つの条件も併せてクリアしないといけません。
- e-taxで確定申告をする
- 帳簿を電磁的記録で保存
特に注意なのは『帳簿を電磁的記録で保存』です。電磁的記録とは各管轄の税務署長の承認を受けたもので、なおかつ一定の要件に合った形での保存が求められます。
つまり
・・・というわけではないのです。もし上記2つの追加条件のどちらかが該当しなかった場合、特別控除は55万円に下がります。
特に
と考えているサラリーマンは、青色申告で65万円の控除が受けられるよう使用する会計ソフトや確定申告の仕方は気を付けてください。
純損失を3年間繰り越せる
青色申告には純損失が発生した場合3年間その損失を繰り越せるメリットがあります。
例えば2018年分の所得がマイナス100万円で2019年分の所得がプラス170万円だった場合、2018年のマイナス分で2019年のプラス分を相殺できるのです。つまり2019年分の課税対象となる所得は30万円・・・となります。
さらに繰越損失は3年間繰り越せます。上記の例だと2018年に出した損失は2021年までマイナス100万円を繰り越せます。
・・・とあくどい考えを持ってしまう人もいるかもしれませんが、3年連続でマイナス所得を申告すると税務署から目を付けられます。マイナス所得の申告が連続して続けば税務署は“脱税”を疑いはじめるからです。
赤字になっても黒字になっても確定申告は正しく申告しましょう。
確定申告をするための帳簿作りが面倒
青色申告をするにあたって大きな障害なのが深刻に必要な書類作成です。中でも帳簿の記帳は簿記の知識がないと抵抗を感じるかもしれません。
青色申告をするためには帳簿の記帳が必須です。しかも先述したように青色申告の特別控除を65万円にするには単式帳簿ではなく複式帳簿で記帳する必要があります。
という人は単式帳簿でも問題ないのですが帳簿がないとそもそも青色申告自体ができなくなります。青色申告をするためには帳簿の記帳は必須なので家計簿をつけるのが苦手ない人は苦労するかもしれません。
白色申告とは?
白色申告とは帳簿に記帳したり保存したりしなくてもできる確定申告を指します。一般的に“白色申告は初心者向け”とも言われています。
白色申告の特徴は以下の3点です。青色申告との違いを踏まえながら説明していきます。
基礎控除以外の控除がない
青色申告には10万円もしくは65万円の特別控除がありましたが白色申告には特別控除はありません。つまり確定申告をしても基礎控除のみしか受けられないのです。
もっとも、白色申告は住宅ローンを組んだり保険料がおりた時などで申告の必要性が出てきたサラリーマンなどが利用するものという意味合いがあります。そのため青色申告に比べて税制上のメリットがないのが大きな特徴と言えるでしょう。
純損失の繰り越しができない
青色申告の場合、課税対象所得がマイナスだった場合3年間はマイナスを繰り越せます。しかし白色申告では繰越損失ができません。
例えば2018年分の課税対象所得がマイナス100万円で2019年分の課税対象所得がプラス70万と申告すると70万円に対して計算された税金が発生します。マイナス所得は節税に使えるので副業を始めるサラリーマンは青色申告で申告した方がおすすめです。
簡単な帳簿の記帳は必要
以前は白色申告の場合帳簿の記帳が不要でした。しかし2014年より白色申告でも帳簿の記帳が義務付けられたため白色申告をするメリットはほとんどありません。
強いて挙げるなら白色申告の帳簿は単式帳簿でも問題がない点。単式帳簿とは1つの帳簿にすべてのお金の流れを記帳する方法で、家計簿とかが該当します。
とはいっても複式帳簿が必要なのは青色申告で65万円の特別控除を受ける人のみで特別控除が10万円でもいい場合は単式帳簿でも青色申告はできます。
そう考えると白色申告のメリットはあまりない・・・と考えてもいいでしょう。
サラリーマンは確定申告が「不要」

先ほど確定申告について青色申告と白色申告の違いと共に説明してきました。しかし多くのサラリーマンは確定申告をした経験がないと思います。
なぜならサラリーマンは基本的に確定申告が「不要」だからです。
税金は申告制のため所得を得たのであれば必ず確定申告をしなければいけません。しかしサラリーマンやOLなど企業に勤務している人は企業が従業員に代わって申告をしてくれているため「年末調整」をするだけで大丈夫なのです。
年末調整とは会社の給与やボーナスから天引きによって納められた税金と本来収めるべき税金を比較し、過不足分をハッキリさせる事を言います。そもそもサラリーマンは給与から収めるべき税金(所得税や住民税など)を天引きされているため確定申告をしなくてもいいのです。
サラリーマンの多くが確定申告をした経験がないのは“確定申告をする必要性がないから”。
もちろん年末調整をしないで確定申告に切り替えても問題ありませんが、特に理由もなく確定申告を自ら行っても全く意味はありません。次からお話しする条件に自分が当てはまってないのであれば無理に確定申告をする必要はないでしょう。
確定申告が必要なサラリーマンの特徴

先述したように多くのサラリーマンは確定申告をする必要がありません。しかしサラリーマンという職業の人全員が確定申告不要か?と言われるとそんなことはありません。
場合によっては確定申告をしないといけないサラリーマンもいます。
中でも以下の5点のいずれかに該当するサラリーマンは年末調整ではなく確定申告をする必要があります。
年収が2000万円を超えた
サラリーマンでも年収が2000万円を超えると会社で年末調整をしてもらえなくなります。年末調整が行われないと配偶者所得や社会保険料控除などの控除が受けられなくなり納める税金が高くなってしまうので確定申告が必要になります。
なおサラリーマンで年収2000万円を超えると受けられない控除がでてきます。例えば配偶者特別控除や住宅ローン控除などは年収2000万円を超えてしまうと受けられません。
・・・とはいってもサラリーマンで年収2000万円を超える人は決して多くありませんし、年収2000万円になる可能性のあるサラリーマンも圧倒的に少ないと思います。該当する人もかなり少数な印象なのでサラリーマンであるうちはあまり気にする必要はないかと。
給料以外の収入が年20万円を超えた
サラリーマンで確定申告の必要性がある人の中で最も該当するのが給料以外の収入が発生している人ではないでしょうか?例えば副業をしているサラリーマンは絶対に確定申告をしないといけません。
万が一確定申告を怠ると給与以外の収入分の税金が納められなくなります。そのため“脱税”とみなされ追徴課税や重加算税などといったペナルティを課せられる危険性があります。
また、テキトーに確定申告をすると副業が会社にばれる危険性があります。
副業で売り上げが発生しているのであれば確定申告は必須ですが副業が会社にばれないように申告する必要があります。会社にばれないようにするための確定申告の仕方については下記ページを参照してください。
複数の会社から給料をもらっている
色々な理由があって複数の会社に所属している場合も確定申告が必要になります。特にメインではない企業からもらっている給料が年間20万円を超える場合は確定申告をしないといけません。
ただし
- 収入金額-所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除は対象外)が150万円以下
- 給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下
の両方の条件を満たしている場合は複数の会社から給与をもらっていても確定申告は必要ありません。
災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている
災害減免法とは自然災害などによって住宅や家財が損失を被った場合、所得税が免除されるものです。免除額はその年の所得金額によって異なりますが、所得金額500万円以下の人であれば所得税が全額免除されるのです。
しかし、損害を受けただけでは所得税が免除もしくは減額されるわけではありません。確定申告によって申告しないと災害減免法が適用されないので、災害等で住宅や家財が壊れた場合は確定申告をしましょう。
不動産を売却した
土地や建物などを売却すれば大金が手に入りますよね?当然不動産を売却した際に得たお金にも税金がかかる可能性があるため不動産を売却したら確定申告が必要になります。
申告するタイミングは不動産を売却した翌年の申告期間(2月中旬~3月中旬)。例えば2019年3月に不動産を売却したら2020年3月中旬までに確定申告を行ってください。
不動産を売却したことで確定申告をする場合、通常の確定申告に必要な書類とは別に以下の書類が必要になってきます。必要書類については売却を手伝ってくれた不動産仲介業者や税務署の職員に詳しく聞いておくといいでしょう。
譲渡所得の内訳書
売却した不動産の概要(土地の面積や区画など)や売却した金額などが記載されている書類。売却が成立してから税務署から送られてくるので、それを見て確定申告書に記入をする
譲渡時の書類
不動産の売買契約書、売買代金受領書、固定資産税清算書、仲介手数料の領収書など。基本的にコピーでOK
取得時の資料
売却した不動産を取得した時の売買契約書、固定資産税精算書、仲介手数料の領収書など。こちらもコピーで大丈夫。また売却した不動産を増改築した場合、下位逐次の請負契約書や領収書のコピーも必要。
売却した土地・建物の全部事項証明書
法務局(登記所)で入手可能。ただし「3000万円控除」と「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」を申告の場合は原本の提出不要。
3000万円控除とは?
不動産を売却した際に発生する所得に対して3000万円まで所得控除が受けられる制度。ただし3000万円控除を受けるためには
- 売却する不動産が自分が住んでいた家であること
- 家屋とともに敷地や借地権を売却すること
- 家屋が取り壊した土地を売却する場合、譲渡契約までの間住居以外で土地を使用していないこと
- 不動産の売却先が特別な関係でないこと(親子や夫婦は適用外
・・・といった条件を満たす必要があります。
取得費加算の特例とは?
「取得費加算の特例」とは相続によって取得した土地、建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合に利用できる特例の事。相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費(つまり経費)に加算できるため相続税が抑えられるようになります。
特に遺産相続で出てきた土地を売却する際に使用できる制度です。取得費加算の特例を利用するには条件があるので下記ページを参照してください。
戸籍の附票
単純な不動産を売却する時には必要ないが「3000万円控除」など各種特例を利用する時に必要。ただし売却前の住民票の住所と売却した不動産の所在地が同じ場合は不要。
確定申告をした方が良いサラリーマンの特徴

先ほど挙げた5つの特徴に1つでも該当するサラリーマンは確定申告をする必要があります。もちろん毎年確定申告が必要な人もいればその年だけ確定申告で翌年以降は年末調整で良かったりもするので
は各自起こった出来事や収入の入りどころを見て判断してください。逆に上記5つの特徴に1つも当てはまらないサラリーマンは確定申告をせず年末調整をしても問題ありません。
ただし、場合によっては確定申告をした方が納税額を抑えられるかもしれない・・・というサラリーマンもいます。
特に次の7つのうち1つでも心当たりがあるサラリーマンは確定申告をした方が良いかもしれません。
家族が自営業を営んでいる
例えばご主人がサラリーマンで奥さんがフリーランスとして活動している場合、会社が配偶者控除や配偶者特別控除を行ってくれないケースがあります。理由はフリーランスである奥さんの収入が年によってバラつきが激しいから。
奥さんの年収にバラつきがあると配偶者控除や配偶者特別控除が受けられない年も出てきます。会社としては処理を素早くするため最初から配偶者控除や配偶者特別控除を行わずに年末調整を出してしまっている可能性があるのです。
と怒りたく気持ちも分かりますが、会社が配偶者控除や配偶者特別控除を行ってくれない以上自分で確定申告をして控除をする必要があります。もちろん会社によって対応は違うので奥さんやお子さんなど扶養家族がフリーランスや自営業を営んでいる人は一度会社に確認した方が良いかもしれません。
住宅ローンを組んだ
マイホームをローンで購入した人は購入した翌年の申告期間で必ず確定申告を行いましょう。なぜなら確定申告をすることで『住宅ローン控除』が受けられるからです。
住宅ローン控除とは住宅ローンを組んで家を購入した際に購入者の金利負担を軽減するために作られた制度です。控除額は住宅ローン残高か住宅の取得対価のうち少ない金額の1%が所得税から控除されます。
例えば住宅ローンの残高が2800万円で住宅の取得対価が2600万円の場合、住宅ローン控除は住宅の取得対価2600万円の1%(26万円)となります。さらに一度住宅ローン控除を申請すると10年間控除されます。
さらに住宅ローン控除額は所得税で控除しきれない部分は住民税から控除されます。つまり所得税+住民税から確実に控除されるわけです。
また消費税が10%に上がってから住宅を購入した場合、控除期間が3年間延長されます。(ただし住宅を購入した期間が令和元年10月1日~令和2年12月31日までの人に限る)
住宅ローン控除については下記ページでも紹介しています。数ある控除の中でも控除額が大きいので住宅ローンを組んで家を購入した際は絶対に確定申告をして住宅ローン控除を申請しましょう。
ふるさと納税を行った
最近いろんな産地の食材や商品を安く買う方法としてふるさと納税を活用している人が増えています。当然サラリーマンの中でもふるさと納税を利用している人はいると思います。
ふるさと納税を利用しているのであれば確定申告をした方が良いでしょう。もっと言えばふるさと納税をしたのなら確定申告は必須です。
ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄附ができる制度の事。寄附をすれば自治体からお礼品としてその土地で取れる食材や名産品が寄附金に応じて送られてきます。
そしてふるさと納税をした金額は住民税や所得税から控除されます。言い換えればふるさと納税で取り寄せた名産品の代金は“税金控除”という形で還元される・・・というわけ。
ただしふるさと納税によって寄附金控除を受けるためには年末調整ではなく確定申告が必要になります。ふるさと納税をしたのであれば
・・・と、忘れないようにしてください。
年末調整をした後に結婚した
例えば会社に年末調整の書類を提出した直後に婚姻届を出して籍を入れた場合、改めて確定申告をした方が良いでしょう。なぜなら結婚したことで『配偶者控除』や『配偶者特別控除』が申請できるからです。
特に結婚して奥さんが主婦になる場合は控除によって税金の還付額が増える可能性があります。確定申告も特別に必要な書類等もないので必要項目だけを記入して提出するだけなので大きな手間はありません。
ただし、結婚後も奥さんが働きに出るとなると話は別です。
- 奥さんが確定申告をしている
- 奥さんの給与が年間130万円を超えている
のどちらかに該当すると配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので、改めて確定申告をする必要はありません。
医療費が年間10万円を超えた
病気やケガなどで病院に通った際に支払った医療費が年間で10万円を超えている場合は年末調整ではなく確定申告をおすすめします。なぜなら医療費が年間10万円を超えた場合『医療費控除』が受けられるからです。
医療費控除は医療費が年間10万円以上になった際に申請できる控除です。控除額は実際に支払った医療費から10万円を引いた金額となります。
例えば年間医療費が20万円の場合、医療費控除は【20万円-10万円=10万円】となります。
また医療費は1人当たりのかかった医療費ではなく“家族”でかかった医療費となります。世帯で合計10万円の医療費を使った時点で医療費控除が受けられるので病院の領収書は捨てずに取っておくように。
仮に自分が全く病院に行かなくても奥さんやお子さんが病気やケガなどをして通院した場合、それにかかった費用は医療費に含まれます。また診察代や薬購入費以外にも通院にかかった交通費も含まれるので通院に使った交通費の領収書も取っておきましょう。
中途退職して再就職をしなかった
退職したものの同じ年に再就職しなかった場合も確定申告をおすすめします。特に病気の都合でしばらく職につけずに収入がゼロになった人は確定申告をした方が良いでしょう。
サラリーマンの納税は基本的に給与天引きで行います。そして年末調整によって払いすぎた分を還付させるのが一般的ですが退職して再就職しないと年末調整ができないため払いすぎた税金の還付ができません。
サラリーマン時代に納めすぎた税金を還付してもらうために確定申告が必要になってきます。別に確定申告をしなくてもサラリーマン時代の給与所得に関する税金は天引きで納めているため問題ないと言えばないのですが
と、納めすぎた税金を取り戻すためにも確定申告はしておいたほうがいいでしょう。
年末調整で申告漏れが見つかった
サラリーマンは確定申告をしなくても年末調整をすれば問題ありません。しかし年滅調整の際に必要な書類を提出し忘れたりした場合は確定申告をした方が良いでしょう。
例えば結婚したり子供が生まれれば家族が増えます。本来であれば結婚や出産があった時は扶養家族についての書類を提出して扶養控除を受けられます。
しかし扶養控除に関する書類(扶養控除等(異動)申告書)の提出をしないと扶養控除が受けられません。もし年末調整の際に扶養控除等(異動)申告書を提出し忘れた場合は、年が明けてから確定申告を行えば扶養控除が受けられるようになります。
扶養控除以外にもマイホームの購入など、年末調整の際に必要な書類の提出を忘れてしまった場合は確定申告をしましょう。せっかく控除によって税金が還付されるなら確定申告をする手間くらい大したことありませんから。
確定申告の具体的なやり方
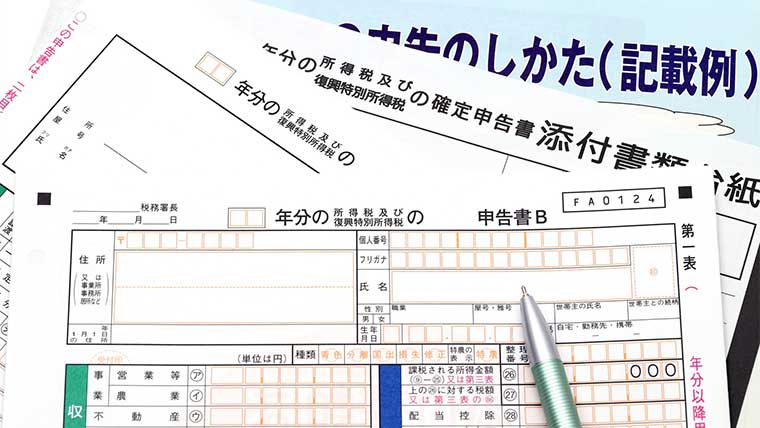
これまでお話ししたように、サラリーマンであっても確定申告が必要だったり確定申告をした方が良い場合があります。もちろんすべてのサラリーマンに該当するわけではありませんし
・・・と、特定の年だけ確定申告に切り替えた方が良い場合もありますので、ご自身の生活環境の変化や収入面の変化に合わせて
を判断してください。確定申告は以下の手順に沿って行います。
1.確定申告に必要な資料や書類を集める
まずは確定申告に必要な書類や資料を集めます。特に必要なのが以下のものです。
確定申告用紙
確定申告をするにあたって最も必要な書類の1つ。なおオンラインで申告する場合は申告用紙を用意する必要はありません。
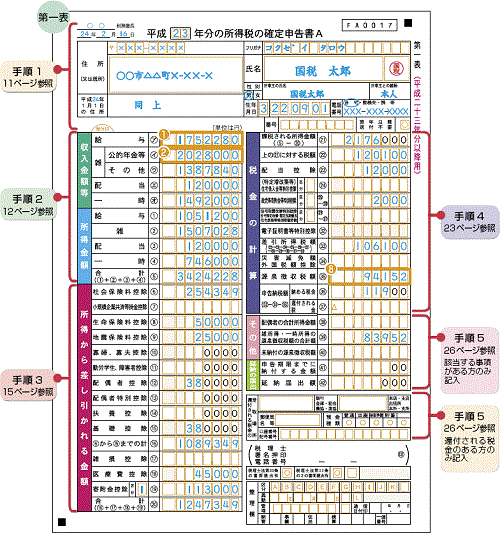
確定申告用紙の種類は大きく分けて4つあります。
- 一般用(白色)
- 一般用(青色)
- 給与所得者の還付申告用
- 公的年金等のみの人用
サラリーマンが控除を受ける際に使用するのは『一般用(白色)』でこの用紙を入手する必要があります。入手方法は税務署に行けばもらえるので、確定申告の相談がてら書類をもらってきましょう。
また、確定申告書にも(A様式)と(B様式)というものがあります。ただB様式は全ての場合に使うことができるため、とりあえず(B様式)を使えば問題ありません。
各種証明書
確定申告をするには申告書に記載した数字を証明する書類が必要です。証明書については手続きをすれば発行してもらえるため確定申告の時まできちんと保管しておきましょう。
住宅ローン控除を受ける場合
住宅ローン控除を申請する場合、以下の書類が必要となります。必要書類の種類と入手先をまとめましたので住宅ローンを組んだ際は下記一覧を見て書類を集めてください。
| 書類の名前 | 書類の入手先 |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署 |
| 住民票の写し | 住んでいる自治体の役所 |
| 建物・土地の登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 |
| 建物・土地の不動産売買契約書 | 不動産会社 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 利用した金融機関 |
ふるさと納税をした場合
ふるさと納税を行うと返礼品と一緒に『寄附金受領証明書』という書類が送られてきます。この書類は確定申告で必要なので必ず保管しておくように。
医療費控除を受ける場合
病院で支払った診察料の領収書は全て取っておきましょう。自分だけでなく家族が病院に行った際の領収書も医療費控除で使えるので家族分をまとめて集めておくといいでしょう。
副業をしている場合
例えば副業をするにあたって必要なものを買った時の領収書は絶対に取っておきましょう。集めた領収書を経費で落とせるか?については確定申告をする際に判断すればいいため、領収書は集められるだけ集めておいた方が良いです。
源泉徴収表
サラリーマンであれば毎年必ず源泉徴収表を会社から受け取るはずです。この源泉徴収表はその人の収入などが記載されているため、確定申告には欠かせません。
万が一紛失した場合は会社に再発行をお願いするか、もしくは市役所で所得証明を取得すれば問題ないはずです。また税務署に相談すればどういった行動かベストなのかを教えてくれますのでその指示に従いましょう。
2.集めた資料を基に必要項目を記入する
必要な資料がそろったら、それらの資料から今度は確定申告用紙に数字を記入していきます。記入方法については税務署にマニュアルが置いてありますし、心配なのであれば税務署に資料全てを持っていけば担当者に教わりながら記入できます。
この時、間違って申告すると納税額が増えたりするので間違えないように気をつけましょう。特に過少申告はその差額の税金に対して加算税がプラスされるからです。しかもその過少申告に悪意がある(わざと過小に申告したなど)と見なされた場合はさらに重加算税がプラスされ、余計に税金を支払わないといけないので記入は慎重に。
3.申告書を提出する
確定申告用紙に記入が済めばそれを提出しておしまいです。提出期間は毎年2月中旬から3月中旬までで、この期間を過ぎると遅延によるプラスアルファのお金が取られることになるので注意してください。
提出場所は管轄の税務署だったり所定の会場だったりします。提出場所については事前に調べておいたほうがいいでしょう。
また最近では各会場にパソコンがあり、そこでインターネットによる申告(e-Tax)ができるところもあります。必要資料だけ持っていって会場でインターネット申告をするのも事前の準備に手間がかかりませんので活用してみてください。
最近の確定申告は『e-tax(イータックス)』
今まで確定申告は上記で説明したような確定申告用紙を使っての申告が主流でした。しかし今後パソコンを使った申告(e-tax)がメインとなっていきます。
e-taxのメリットとしては
- 自宅から確定申告が可能
- 24時間いつでも申告できる
- 書類の添付が不要
などが挙げられます。サラリーマンの場合
という人も多いため、個人的にはe-taxで申告した方が良いと思います。
特に副業に取り組んでいるサラリーマンやこれから副業を検討しているサラリーマンはe-taxでの申告が必須になります。e-taxで申告しないと青色申告の特別控除が65万円にならないですから。
e-taxでの申告は国税庁のホームページからできます。またe-taxでの申告の仕方についても説明ページがありますので一度確認してみてください。
まとめ
いかがでしたか?サラリーマンにとって確定申告はなじみが薄いですが、タイミングや収支状況によっては確定申告をした方がお得になったり確定申告をしないといけなかったりもします。
色々聞きなれない単語が多いため
と感じるかもしれません。しかしやってみると必要なところに数字を書き込むだけですので割と簡単にできます。
また確定申告について分からなかったら税務署に行って質問するとかなり親切に教えてくれます。まずは自分に確定申告の必要性があるか?から調べてみてください。